“原作が落語的だったので、そこは意識しましたね”『憑神』降旗康男監督インタビュー
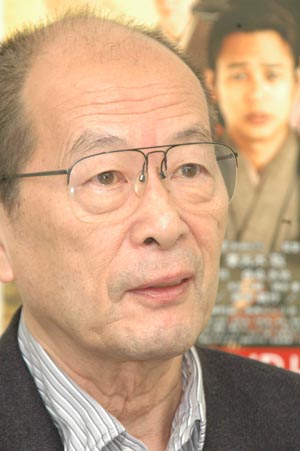
『鉄道員』から7年—。浅田×降旗コンビで人間悲喜劇に挑戦
時代小説から四次元小説まで日本人を描いて読者の心を魅きつけて離さない作者・浅田次郎。誠実にそれぞれの人生を生きる無名の庶民の心を描き続けている映画監督・降旗康男。1999年浅田×降旗コンビで製作された『鉄道員(ぽっぽや)』は270万人を動員。日本中に感動の嵐を巻き起こした。それから7年—。今回は、お江戸に生きた、最後の侍を、笑いの中にみずみずしく描き上げた『憑神』が原作。
時は幕末、下級武士の別所彦四郎。学問所では優秀であったが身分制度に縛られ身動きできず、その上婿養子先から追い出され、もはや困ったときの神頼みと拍手打った神様が悪かった。何と現れたのは“貧乏神、疫病神、死神”の憑神様だった。
主人公・彦四郎役は『涙そうそう』『どろろ』と主演作品が続く俳優・妻夫木聡。降旗監督作品に出演したいという妻夫木聡の想いが監督に届き、また、監督もこれまでは青春真っ只中の瑞々しい若者像を演じてきた妻夫木に「今回は青春を謳歌できない、だからこそ輝く役を演じてほしい」と出演を熱望し、本格的に映画化がスタートした。また貧乏神、疫病神、死神役をはじめ日本を代表する多才なキャストが終結し、新境地に挑む妻夫木聡をサポートする。
神に愛された男を通して日本人の“誇り”と“負けっぷり”を描いた降旗康男監督にお話を伺った。
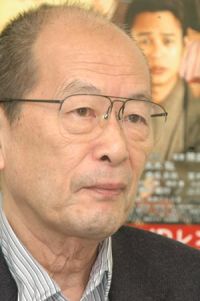


『憑神』は降旗監督の作品としては、いつもよりも軽妙でしたね。
「そうですか。軽くないのは高倉健さんの方で。僕はいたって軽いタイプなんですがね(笑)。原作が落語的だったんで、お客さんにも落語的に受けとってもらえたらいいかと思ったんです。そういうことは意識して作りましたね」
監督は落語はお好きなんですか?
「落語全般が好きというわけではないんです。大学に入ったときに同級生に連れていかれたのが古今亭志ん生だったんですよ。だから落語というよりは古今亭志ん生に惚れてしまったわけで。お酒を飲んでるんじゃないかというような、デレッとしながらも動くところはしっかりと動くというのがとても好きで。それから大阪の(桂)枝雀さんがお気に入りでしたね。私はこの2人だけで、他の人はあまり知らないんですよ」
今回の映画に古今亭志ん生さんの影響はありますか?
「むしろ今回の作品は桂枝雀さんですかね。もう言葉だけじゃ足りないぞというくらいに、全身を使って話をするという。むしろそっちの方に似た話なのかなと思いまして。桂枝雀さんの落語もいろいろとDVDで出ているので、今回の映画に合わせて見返したりしました」
西田敏行さんが出てるシーンなんて特に落語的というか、テンポがいいんですよね。
「どうしても西田さんにやってほしいところでしたからね。スケジュールがまったくないところを無理矢理4日間だけ空けてもらって。それも朝に新幹線で来てもらって、夕方に新幹線で帰るということでやってもらったわけですよ。普通のやり方では間に合わないですからね。
そういう部分で、どうやってテンポをよくしたらいいのだろうかというところで、なるべく長く回した方が全体のテンポが出るのかなと思ったんですよ。そんなのも時間のなさという困ったところから生まれたわけですよね」
この映画は妻夫木さんが降旗監督に惚れこんで生まれたいうことですが。
「惚れこんだというよりは、一緒に何かをやろうじゃないかということですよね。最初は別の企画で一本あったんですけど、それがうまくいかなくなってしまいましてね。妻夫木くんの撮影期間は確保したので、彼を主演に何か題材を探してくれということになったわけです。そこで、何人かのプロデューサーとで題材を探してるうちに、ちょうど浅田次郎さんの『憑神』が出版されたんですよ。
ただ妻夫木くんが10歳くらいの子供を持つ父親ということで、年齢的にはちょっと違いますけど、昔だったらありえる話だっただろうということで始まったんです」
監督はこの作品以前に妻夫木さんの作品を観ていたんですか?
「『ウォーターボーイズ』とね、それから『さよなら、クロ』という映画ね。あれは僕の出身校が舞台になっている映画なんですよ。2本だけ観ていて、『さよなら、クロ』の妻夫木くんがいいなと思ったんで、一緒にやってみたいなと思っていたんですよ」
この映画は3人の神さまたちのキャスティングが肝になると思います。どのあたりを考えてキャスティングを進めたんですか?
「死神、貧乏神、厄病神。それぞれ痩せこけていたり、怖かったりというところとは全くかけ離れた方が面白いだろうと思ってね。貧乏神だったら金持ちの商人。厄病神は丈夫な相撲取り。死神は可愛い女の子という反対のイメージでいきたいと思ってました。それはもちろん原作でもそうだったんですけど、それをキャスティングでもうひと押しすれば、そのギャップが面白くなるだろうなと思いました。
ただ、相撲取りだけは難しかったですね。本当なら西田敏行さんより体格ががっちりした人がいいんでしょうけど、そういう人はなかなか存在しないし。僕は相撲に詳しくないんだけど、ちょうど去年の春場所くらいに、ころころ負けてたあの大関(注:おそらく魁皇だと思われる)がいいなと(笑)。テレビのインタビューでけっこうベラベラ喋っている人だったので、あの大関が引退したら頼めるかな、なんて言ってたんですけど、彼もまだまだ現役ですからね。駄目でした」
とはいえ赤井さんの厄病神も非常に面白かったですよね。
「そうですね。赤井さんもすごく力士の雰囲気を出してくれました。かつ赤井さんの大阪弁でやってもらった方が面白さが出るだろうなと思って。そこは設定を変えてうまくいったと思います」
赤井さんが鼻をほじるシーンが面白かったですよね。
「ちょうど外国人の翻訳本で『鼻くそ言論』という本を読んでいたので、厄病神役が誰になっても鼻をほじってもらおうと思ってたんですよ。
赤井さんの場合は鼻くそをほじって飛ばしたいんですけど、というくらいで。飛ばしたあとに指を舐めましょうか、と言ってたんだけど、さすがにそれはちょっと汚らしいからやめてもらったんですけどね(笑)」
死神役の森迫さんも可愛かったですね。
「テレビの『ちびまる子ちゃん』の子でね。最初のうちは妻夫木くんよりセリフが入っててね。それは入っているだけでなく、ちゃんとその時の状況に合わせて芝居をしながらやるわけです。妻夫木くんもタジタジとなったのではないですかね。達者でかつ面白い。とてもおかしなキャラクターだったと思いますけど。人物のキャラクターを理解する力と、セリフをパッと覚える力はたいしたものだなと思いました」
妻夫木さんはついていない侍ということで、いろんな人が共感できるキャラクターなんじゃないかと思うんですが、そのようなことをどのように込めました?
「まあ疫病神や死神はともかく、貧乏神は10人いれば9人くらいはとり憑かれているんじゃないかというモンですからね(笑)。そういうところはスッと入ってもらえるんじゃないかと思いました。そこでスッと入ってもらえれば、疫病神も死神のところにも繋がっていけるのかなと思いました」




最後のクレジットは、スタッフ、キャストとも手書きのようでしたが、これはそれぞれに書いてもらったんですか?
「そう。ひとりひとりに書いてもらったんですよ。それぞれが責任を持つため、というのは冗談ですけど(笑)。
結髪の女の子が、冗談で木村大作(本作のカメラマン)の似顔絵を風船に書いてパチンパチンとはじいて遊んでいたんです。とてもうまいんですよ。そこでそれぞれの技師さんの似顔絵を描いてくれよと言って。ひとりにつき10枚くらい描いてもらったのをデジタルで取り込んで、パッパッと変えたんですけどね。昔のフィルムの技術ではあんなことはやれないですね。デジタルの技術がなければ。まあ落語風に始まった物語の終わりとしてはいいんじゃないんですかね」
あれは遊び心に溢れたエンディングでしたね。木村大作さんの名前がはじける部分がありましたけど、あそこはどういうところから?
「あれはみんなに嫌われているからですよ(笑)。みんなに蹴飛ばされて飛び散るという」
妻夫木さんのインタビューなどを読むと、監督はあまり指示をしない人だということが書いてありました。あれはどういう意図があってでしょうか?
「特に意図はないんですけどね。僕も昔は怒鳴っていたんですけどね。だいたいワーワー言うのはカメラマンか監督ですよ。だから二人でワーワー言ってたらどうしようもない。ひとりワーワー言うのがいたら、ひとりは言わない方が現場がスムーズにいくという。ただそういうことなんです。もう20数年間。木村大作と一緒にやるようになってからは横で黙っているようになったわけです」
監督と木村大作さんは名コンビだと思うんですが、監督の考える木村さんの良さって何ですか?
「画面をどう撮ろうかと相談するときに、撮りたい位置が僕と大ちゃんとが一緒であることが多いんですよ。僕が助監督をやっていた時なんか、監督とカメラマンが正反対の位置に立っているなんてしょっちゅうあったんですけどね。
俳優さんの動きがだんだんと固まってくると、僕と大ちゃんの立つ位置が同じところになるというのが、僕と大ちゃんが長続きする秘訣なのかなと思いますけどね。気心が知れているというか、ものを見る目が似ているんだろうなと思います」
今回セットがすごく良かったですね。
「ああ、あれも怪我の功名でね、先に『大奥』が入っていたんですよ」
ああ、あのセットに1億円くらいかけたという。
「ステージを全部占領されてしまってね。話の半分は妻夫木くんの住んでいる家なんだから、本当はセットを作りたいんだけど空いているところがない。そこで、オープンの空き地に中の様子も撮れるように屋根のついた建物を建てようということになったんです。その結果、庭から通して奥が撮影が出来るようなセットになったということになったんです。普通なら庭の部分だけ表に作って、中は両方セットということになるんだけど、そうすると庭を通して向こうの家を写すというようなことも出来ないわけですよ。もちろんデジタルで合成すれば出来るかもしれないけどね。
そういうのが全部出来たというのが怪我の功名なんですね。ただその横に山陰本線が通っていたんですよ。だから踏切の音にかぶらないように時間を調べるわけです。『今度の間隔は7分です』なんて言いながら、ちょうど11時から12時頃でしたよ。しかも11月から12月なんて、もみじのシーズンなんで山陰線で臨時列車が出るわけですよ。制作の人が調べたのが駅の時刻表だったから、『この次何分です』なんて言ってるんだけど、関係ない時間に電車がいくつも来るわけです(笑)。
妻夫木くんが錆びた刀を研ぐように頼みに行くシーンなんて何回やったんだろう。10数回くらいやったかな。いいところになると踏切の音が鳴るわけですよ。いささか彼もふくれてたけどね(笑)。でもしょうがない。そんなこともありましたが、ずっとつなげて見せることが出来たので良かったと思います」
では最後に観客の皆さんにメッセージをお願いします。
「笑いながら、笑っていく中で責任とは何だろうということがちょっとでも思い浮かべていただけるといいなと思います。でも一番望むことは笑って楽しんでいただきたいということですから。その笑いがすっと気持ちのいいラストになっていただければいいなと思います」
執筆者
壬生 智裕