「起点である70年代に立ち返り、これまでの総括をやってみたくてね」 『またの日の知華』原一男監督合同インタビュー
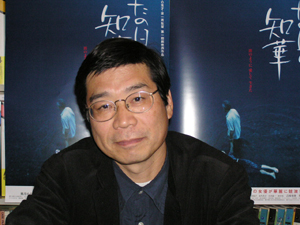
『ゆきゆきて、神軍』、『全身小説家』など、観る者を圧倒するパワフルさに満ちたドキュメンタリーを世に問うてきた、原一男監督の新作『またの日の知華』がいよいよ1月15日からロードショー公開される。今回の作品は、激動の60年代から70年代を背景に、知華という一人の女性の生き様を描いた、ドキュメンタリーの鬼才初の劇映画なのである。全体が知華の年齢ごとの4つの章+エピローグからなる本作だが、実は各章ごとでヒロインを演じる女優が全く異なっているのだ。それぞれに個性的な女優陣によって演じられた知華は、彼女が関わった4人の男が観たそれぞれの知華像を体現しながらも、作品を通して観た時の違和感の無さは本当に意外な程だ。そこには原監督の、劇映画のフィールドでも挑戦的な映画作りを続けて行くことを、高らかに宣言ししているかのようだ。本作を、これまでの自作の総決算として位置付け、さらなる地平に向おうとしている原監督への合同インタビューの模様をお届けしよう。
$navy ☆『またの日の知華』は、2005年1月15日より、シネマスクエアとうきゅうにてロードショー公開!$


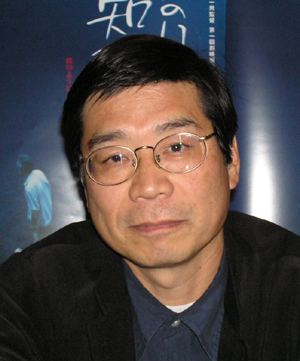
——初の劇映画として、知華という女性を巡る物語を題材に選んだ経緯をお聞かせください。
「今までドキュメンタリーをやってきましたが、最初の『さよならCP』では主人公たちは男ですけど、中でも強烈な印象を残すのは横田弘さんの奥さんであり、次の『極私的エロス・恋歌1974』はもろ女ですよね。3作目の『ゆきゆきて、神軍』は勿論奥崎謙三さんが主人公ですけど、奥崎さんの奥さんという存在がちょっと不気味な存在として印象に残る。『全身小説家』も勿論主人公の井上光晴さんは男なんだけど、あれはまさに女の人たちが沢山でてきますよね。だからどこかで、男と女という関係を一つの作品の中で描かないと気がすまないというのが自分にはあるのだと思います。基本的にはね。
それと今までやってきたドキュメンタリー…アクション・ドキュメンタリー、スーパーヒーロー・シリーズの二つと僕は言っているのですが、その“スーパー”という生き方、非常に個としてのパワフルな生き方を全面展開していくという生き方を、80年代に奥崎さんで撮って、90年代に井上さんで撮ったわけですが、今やああいう作り方が成立し得ない、ああいう生き方がもう時代の推移と共に終わったんだという感覚があったんですよ。4本の作品で、問題意識が一巡し終わってしまったので、次のステップに螺旋状に登って行かねばならないという課題があると思って、二巡目に行くにあたって今までやって来たことの総括をやってみたくなったということと、女の人を描いてみたくなったんですよ。これまではずっと、男をメインでやってきましたが、女の人をメインに撮ってみたいかなと。
そしてもう一つとして、70年代を起点に30年以上生きてきて、もう一回二巡目に入るに当って、そういう総括をしないと、次にどういう風に生きていくのか、どっちの方向に映画を撮って行くのかがよく判らない感じがあったんです。そういうことを、今回の劇映画の中でやってみようと考えたんです。
それと日常的には、あんたは女が判っていないと言われ続けてきたもんですからね。よし、それじゃ女を描いてみようじゃんと言うような意地をはってというところもあったりしてですね(笑)、いろんな要素が絡んで今回は女を描こうよという風になったんです」
——これまでのドキュメンタリーと今回の劇映画では、撮影・演出等のスタンスで異なる部分はありましたか?
「僕らのこれまでのドキュメンタリーの作り方は、決して主人公達が生きている日常生活を客観的に随伴し、伴走して撮っていくようなものではないですよね。貴方達の映画を撮るんだから、やりたいことをそこで見せてくれ、というのを際立たせていくやり方でしょ。必然的に、どんな風に演じてみせてくれるのかという興味を持って、カメラで凝視して行くというスタイルなんです。だからその感覚から言えば、劇映画もシナリオという仕掛があるのだから、基本的には俳優さんがそれを読んでどんな風に演じてくれるんだろうなという風に思っていたんですよ。
でもそう言いながら、全く矛盾したこともやってるんです。渡辺真起子さんの件を撮っている時に、渡辺さんの演技のパターンではなくて、二章の知華さんに関してはこういう風に演じて欲しいというのが結構強くありまして、テストを何回も繰り返して私の持っているイメージをやって欲しいということを、やってみたりしもましたね。それで彼女は、テストを繰り返し繰り返しやったんですが、途中で泣き出しちゃって。その場の撮影は何とか終わったんですが、その後で話したいことがあると言われまして、色々話をしていく中で、やはりその女優さん、その女優さんで、自分の一番いい演じ型のパターンは違うんだということが判ったというか、彼女に教えられたような感じでした。
そういう意味ではドキュメンタリーと同じで、どんな風に演じてくれるのかなということ、自由に演じてもらっていいんだという所にもう一度戻っていく感じはありましたね。だから劇映画とは俳優さんのドキュメンタリーであると言う、諸先輩から言われてきている言葉と感じは近かったかもしれません」


——四人の知華さんはどのようにキャスティングされましたか?
「桃井さんとは、クランクインする2・3年前に別の要件で会って二人で話をした際に、劇映画をやりたいと思っている。一人のヒロインを4人の女優でやりたいんだってことを話すと、彼女がえらく興味を持ってくれましてね。「私、それやりたい。やらせてよ。きっと私やる。うん、きまり。私それをやる」って、そんな感じで彼女の方が言い切ってくれましてね。そういう出会いです。それで4人目の知華さんが先ず決まった。
3番目の金久美子さんに関しては、『全身小説家』がベスト1になって表彰式で顔を合わせた後、二人で飲んだ時に劇映画をやる時には必ず一緒にやろうねという約束があって、これはもう3番目の知華さんであると。
それから2番目のキャスティングに入っていったんですが、誰がいいかなと思案している時に『M/OTHER』と『2/DUO』の渡辺真起子さんはどうかなと思って。つまり僕らなりに、心意気でやってくれる人という基準があったんです。予算が大きな作品というわけでもなかったですし。それで会って見ようよということになったら、真起子さんの方でもやらせてもらいたいと言ってくれて、2番目の知華さんが決まりました。
それで、最初の知華さんが一番最後になったんです。色々迷ったんですよ。一番迷ったんじゃないかな?吉本多香美さんに会おうと思ったのは『皆月』という映画で話題になってまして、見に行っていい女優さんだなと思っていたのです。それでまず会ってみようよと言うことで、シナリオを読んでもらって話をしたら是非やらせて欲しいと決まりました。」
——個性の異なる4人の女優さんが一人のキャラクターを演じているわけですが、キャラクターに関して共通したイメージをといったような演技指導はされたのでしょうか?
「いや、細かい部分での演技指導は、あまりしてないですね。先程お話した真起子さんにしても、やりたいようにやってもらった方がいいんだと思ってからは、そのように関わり方を変えました。それぞれの女優さんにある持ち味と、知華さんをどんな風に演じてくれるのかという掛け算みたいな部分で成立して行くといいなという感じはあって。それはそれで、それぞれの人が自分の解釈はこうなんだと言う風に探りながら、いろいろやってくれたんです。それを見て、知華さんにはこんな面もあるんだなとこちらも思ったりしながら、現場をやっていた感じですね」
——劇中では、落ちてゆく感覚が繰り返されますが、知華さんと落ちていくイメージというのは、日本の国とも繋がっているのでしょうか?
「知華さんみたいな生き方には、堕落していく、転落していく女の物語という見方が一つにはありますよね。でも僕らとしては転落していくという捉え方ではなくて、解き放たれていく、解放されていく物語を撮ろうというのがありました。解放されていくというのは、つまり我々はしがらみをいっぱい持っていますが、そこから遠く遠く離れていくと言いますか、遠ければ遠いほど自由になって行くというイメージがあるわけですよ。
ただ解き放たれていって、この現実の世の中にユートピアがあるはずは無いじゃないですか。だから、自由になっていっても、絶えずしがらみみたいなものは追いかけてくるので、その究極の形として殺されるかもしれないという予感はあったのかもしれない。それでも、そっちに向って生きていく。自分の意志で選んで生きていくというイメージがあってね。要するに殺されなくてもよかったんですが、もともとヒントになった事件も殺人事件ですし」



——知華さんは4人の男性全てに対して満たされず不甲斐なさを覚えつつも惹かれて行くわけですが、それは女性ならばこそそうなって行ったのでしょうか?それは、60年代・70年代がバックになっている時代背景にも関わっているのでしょうか?
「シナリオライターである小林佐智子の狙いとしては、一章では血の繋がった兄という関係に対して知華さんが惹かれて行くというようなことがそれぞれの章にあって、四章の夏八木勲さんは父という幻想であり、三章の小谷嘉一君は弟という幻想であり、とそれぞれに意味があります。我々の肉体というか存在を縛っている幻想みたいなことの追求をやりたいという欲求があったということが一つにありますね。
それと、時代背景は70年代で、本編中に様々なニュースフィルムが流れますが、あれは単に背景の時代説明になっていたら、作り手側の負けであるという風に思っていたんです。知華さんそのものは、直接政治という行動には参加してませんが、その時々の重要な事件があって、それに見合ったような形で自分の生き方を選んでいっていることにリンクする形で挿入されるように、構成が組み立てられているはずです。だから決して現実の政治活動をしているわけではないのですが、70年・80年という時代の中を知華さんが駆け抜けていくという感覚は、現実に僕らにもあったものなので、それを映画でやってみようという感じはありました」
——知華さんの周りにいる男達には、監督ご自身の内面も投影されていますか?
「投影されてるんじゃないですかね(笑)。それこそ渡辺真起子さんに、田辺誠一さんから電話がかかってきて彼女は会いに行きますが、あの時田中実さんは止められなかった。止めるという風に体が動かなかったでしょ。あれは正しく、現実の体験です。そういうのが随所にある筈です」
——ポスター・ビジュアルにもなっている場面が素晴らしかったですが、撮影についてエピソードをお聞かせください。
「これは飛島の外側で撮影しているのですが、シナリオでは血のような真っ赤な夕陽を背景にしたものだったんです。撮影当日は天気がいい日でついてるな…と思っていたんですが、そろそろ撮影という時に雲がかかってきてしまったんですよ。それでもギリギリまで粘ってみたんですが、中々雲が切れてくれずスケジュール的なこともあり兎に角撮ろうってことになり、曇ってる状態で撮ったのがこの映像なんです。
ところが、撮り終わった直後に晴れたんですよ。桃井さんは濡れた服から着替えたところだったんだけど、カメラマンが走っていって「晴れた!やりたい?」と聞くと、彼女も「やるわ!」と言ってくれて、急遽シナリオの指定どおりにも撮ったんです。でそれはそれでなかなか良かったんですが、仕上の時に両方繋いでみたらやっぱりこっちがいいよねって話になりましてね。それでで、こちらを使ったんです」
#——エピローグをつけられた意図は?
「いらないんじゃないかという考え方は、僕らの中でもあったりで色々迷ったんですが、でもこうして形になってみると、やはりあれは必要なんだということですよね。息子というのも、息子でありながらやっぱり男であるという。元元の発想が、私が男で、私が息子で、自分の母親という存在と関わってきた女達を描きたかったわけだから、作り手にとってはあれはいるのだという結論を出したんです」
——最後に一瞬現在の東京の映像が映って終わりますが、意図的なものでしょうか?
「それ程的確に、あの映像を狙って撮ったというわけではないです。ぶっちゃけて言うと、これにも色々紆余曲折があって、一番最初は息子が飛島を訪れてまた船着場に戻ってくる映像を撮りたかったんですが、撮影中断を挿んで実際にロケに行ってみたらビルが建て替えられてしまって、時代考証的に撮影ができなくなってしまったんです。最初のシナリオでは、純一が戻って来てその船着場でトラックに乗って行こうとする時に声をかけられるんです。それが知華さんそっくりの女性で、乗せてくれない?って言われて、いいよと乗せてあげて走り去るというのを考えていたんです。
ところが撮影できなくなってしまったので、どうしようということになって、色々悩み、都会に舞台を持ってきて雑踏の中で純一と肩触れ合って、見てみると知華さんそっくりの女性だったみたいな。そういう風に撮ろうと、一度は決めたんですが、よくあるパターンよねって桃井さんに言われて、それもその通りなんですよね。どう撮ったって、よくあるパターンなんですよ。それで、散々悩んだ結果、カメラマンがアイデアを出したのかな?都会の雑踏じゃなくて、築地で飯を食ってることにしようってことになって、そうしたら桃井さんが、だったら知華さんじゃなくて桃井かおりでいいんじゃない?って言ったんです。桃井かおりと吉岡秀隆君でいいんじゃないか、それでやろうって。最後はドキュメンタリーでいいんだと、そういう壊し方って今時の映画には必要でしょって彼女が主張して、私も基本的には人の話を聞くタイプですから(笑)、じゃぁやってみるかってことになったんです。
ところがね、繋いでみたんですが、やっぱりこれが繋がらないんですよ。長いシーンになってしまって、ドキュメンタリーとしてそのシーンが面白いかと言えば、然程面白くない。やっぱり違うんじゃないかなと思って捨てたんです。結局、本来の純一と知華さんに似た人が出会うという映像は成立しなかった。でも無いんだからしょうがないから、走ってるところで終わろうということになったんですが、終わってみれば不思議に意味が出てくるじゃないですか。映画って言うのは、どういうつなぎ方をしてもね。こういう終わり方もあるよってね。私としては現在の息子という存在を、どうしても映像として入れたかったということです」
——一つの決算ともいうべき本作を完成され、今後はどのような作品を撮りたいですか?
「ドキュメンタリーもやっぱりやりたいですね。今まで作ってきた流れじゃない方法を見つけないといけないなと思って、現在二つくらいとりかかってはいるんですがこれも、2・3年かかるものだと思います。一つは、70年代くらいに頻発した嬰児殺しを題材にしたもので、もう1・2年取材等で動いています。事件そのものを描くというより、フォークロア的な観点から描くことができないかと、模索をしています。
それとドラマも勿論やりたいと思っているんですが、次は兎に角チャンバラ青春時代劇、国定忠治をやろうという風に気持は固めています。でも、それは結構大作になるだろうからと、その仕掛をそろそろ画策し始めたところです。未だ何年も、先の話になるかと思いますけどね」
本日は、どうもありがとうございました。
(2004年11月30日 疾走プロダクションにて)
執筆者
殿井君人