きっかけは“家庭教師もの”!イメクラ嬢が大陸間弾道爆弾の秘密に・・・『花井さちこの華麗な生涯』女池充監督インタビュー

イメクラ嬢さちこが額に流れ弾を受けたことで天地開明し、猛烈な知識欲に襲われ天才的な頭脳を発揮し、しまいにはアメリカ大統領の隠した大陸弾道爆弾まで発見するという、「何それ?」なトンデモ系怪作『花井さちこの華麗な生涯』が11月26日からポレポレ東中野で公開されている。
大統領の指をめぐっての某国工作員に追われることとなった主人公さちこが魅せるアーパー娘から博覧強記な知の巨人(でもインラン)への豹変ぶり、愛すべき登場人物たちが繰り広げる深刻なんだか軽薄なんだかわからないポリティカル・コメディ。監督は、文化庁の支援でニューヨーク留学から帰って来たばかりの女池充さん。海外の多くの映画祭で上映され、熱狂的な支持を受け、満を持しての凱旋上映となった。



海外の映画祭での反応はいかがでしたか?ブッシュ大統領が登場しますよね。
「政治的なことと裸がひとつの映画に入っているというのが珍しかったみたいですね。向こうでは裸が出てくる映画はそれだけ!ってスパッと切れているみたいなんです。昔ラス・メイヤーとかもいましたけど、結構キリスト教って大きいみたいで、そういう映画をまったく観ない人もいて、人の裸なんて見た事ない、なんてこともあるみたいですよ。」
国によって反応の違いは感じましたか?
「上映に立ち会えたのはドイツとアメリカのニューヨーク、シカゴ、オースティン(テキサス)だったんですが、反応も聞かれることもそんなに差はなかったですね。映画祭に来るお客さんて、もともと映画好きなのでなんでも偏見なく観てくれるみたいです。ドイツでは、会場で瓶ビールが販売してたんですが、上映中その瓶が転がってゴロゴロゴロゴロずっと鳴ってたんですよ(笑)。飲み終わると足元に置いて、それがどうも足で倒してしまうみたいで。でも映画はすごくウケてました。」
映画祭ではピンク映画だった時の60分ではなく長尺版での上映ですが、作品としてはどういうところが違いますか?
「60分のものを作ろうと思って撮影はしてたんですが、撮影が終わってつないでみたら90分になっちゃってた。ピンク映画は60分という規定があるので、主役のさちこを追う伊藤猛さん演じるキムのエピソードシーンをカットしてます。さちこの部屋に忍び込んで彼女の帰りを待ってるうちに、掃除をし始めたり、洗濯したり、ご飯食べたりっていう場面ですね。」
脚本は中野貴雄さんですが、どういった経緯で監督されることになったんですか?
「“家庭教師もの”ということで会社からオファーされたのがはじめなんですが、それと別に中野さんがサトウトシキさんのために書いた脚本があって、トシキさんが引越しかなにかで荷物を片付けていたときにひょっこり出てきて、読み返したら面白いということで僕も読ませてもらったんです。でもそれは“痴漢電車もの”だったんですよね。なんとかこの“痴漢電車もの”を“家庭教師もの”として変えられないかと思ったんですが無理で、再度新たに作ってもらおう、というところからはじまりました。」
脚本のベースはお二人でつくっていったんですか?
「もう中野さんのアイデアだけです。中野さんは普段からいろんなアイデアがとめどなく出るタイプの方なので。喫茶店で中野さんとお話しながらふっと出てきたアイデアに「それ面白いですね。」って僕がゆったのが、女の子が喫茶店で流れ弾に当たっちゃうんだけどなぜか死なないで済んで、逆に頭よくなっちゃって、それで家庭教師になるっていうところです。そこから膨らませてもらったのが、今回の作品です。でもなかなか出来なくて。2月に話をしてて5月公開だったんですが、結局台本が出来たのが5月で公開が夏に延びた、でも撮影してたのは夏で、公開は結局11月だった。準備も大変だったし、主役候補がなかなか見つからなかった。やっとなんとかめぐりあえたのが黒田エミさん。彼女のスケジュールもなかなか合わなくて、普通ピンク映画は1週間ですべて撮り終えるんですが、半分ずつ間を空けて撮ったんです。」
さちこ役にはかなりのこだわりが?
「ピンク映画に出てくれるような人も少ないですし、巨乳の女性がよかったんですよ。もう巨乳が主人公ってだけでコメディになるんじゃないかと思って。でも、なかなかそれが難しくて。巨乳だけって人だったり、面白い人だけど胸が小さかったり…。胸は小さくてもいいかー、とも思いましたけどピンク映画なんで多少はあった方がいいかとも思ったり。時間かかっちゃいましたね。黒田さんは今はプロの格闘家ですけど、演技をしたのはこの作品一本きりなんです。中野貴雄さんのVシネにちょっと出たりはしてたみたいですけど、本格的なお芝居はこの作品だけ。」
長台詞も多かったですし、いっていることも「ノーム・チョムスキーがどうだ」とか「弁証法」がどうで「サルトルいわく・・・」みたいな難解な哲学思想ですね。黒田さんが非常にかわいらしい声なので難い台詞とのギャップもおかしいですよね。
「初めての芝居なので、台詞もそんなにしゃべれなくてもいいやと思ってたんです。芝居がちゃんとできる役者さんだったら嬉しいですけど、こういう映画だしこういうキャラクターの女の子だし、そんなに演技とか要求しないでおこう。出来なかったらそれは現場で考えよう、と思ってた。クランクインしたのはキャスティングしてから1週間ないくらいで、その間も彼女は別の仕事をしていたのでほとんど打ち合わせもできなかったし、台本を覚えているような時間もそんなになかった。その日その日やることを現場でやってもらうしかないような状況でした。一番最初にとった場面が、知性に目覚めたさちこが難しい数式を街頭に書き殴るっていうシーンで、いろいろ訳わかんない台詞をいっぱいしゃべるんですよ。そのシーンも、ペラペラ話せててびっくりしました。サービス精神が旺盛で、頑張り屋で、うちらスタッフなんかよりもずっと肝がすわっているんです。かなりしんどかったとは思うんですが迷惑かけちゃ悪いと思って頑張ってくれていたんだと思います。」
出来上がった中野さんの脚本をいよいよ監督される時ってどう思いましたか?
「僕ってなぜかよく「こだわりがある」とかゆってもらったりすることが多いんですが、単に幅が狭いんです(笑)。だから、本をよんで撮りたいプランが浮かんで、でもそれが難しいってなっても他に方法がなかなか思いつかなくて。予算もないので、アイデアでもっと面白く作れたらいんですけど、結局アニメをつかったり人形を出したりとか…。選択肢がない状況でした。」


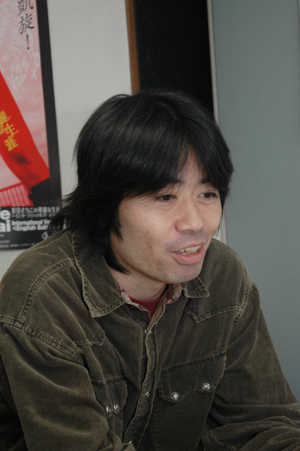
映画監督の松江哲明さんがさちこの生徒役で出演されていますよね。童貞の若い学生という設定が不思議と松江さんにピッタリでした。変なTシャツを着ているのが気になりましたが…
「実は伊藤猛さんが「まっちゃんこの役、いいんじゃない?」ってゆってくださったんです。松江くんは永遠の高校生というか永遠の童貞のような人なのでバッチシだと思いました。高校生の役だったんですが、年齢とかそういうところではなく、彼のキャラクターがこの役そのままでした。衣装はすべて松江くんが自分で用意してくれたものだったんですが、さちことの絡みのシーンで着ているのは彼が出演した『ばかのハコ船』(山下敦弘監督)と同じTシャツ(笑)。僕もあの映画が大好きでかなり衝撃を受けているので、あやかろうかなと。」
黒田エミさんも変なTシャツ着てますよね。
「ぬるま湯Tシャツ(笑)。あれも彼女が「着たい」ってゆったんです。あのTシャツは彼女ももっててもなかなか着る機会がなかったからってゆって持ってきてくれたものです。ピンク映画って衣装はほとんど役者さんの自前なんですよ。本人が持っているものの中で映画に合うものをチョイスしてもってきてもらうんです。シーンによっては汚れちゃったりするので、もう着ない服をもってきてもらうこともあります。」
撮影で印象に残っていることは?
「屋上でブッシュがテレビに出てくるシーンは、夕方でもう暗くなっちゃうので時間がなかった。自分としては、もう無理だと思ってて別の日に撮りたかったんですが、なかなかそうもいかなくて。てんやわんやになりながら撮ったシーンなので、もうちょっと色々やり様を考えたかったなぁ。ニューヨークでもあのシーンはウケてた。ブッシュが出てくるシーンではほとんど大爆笑されてたんですが、あのシーンは特に映画の音が聞こえなくなるくらいの反応でした。(ブッシュを)嫌いな人多いんだなぁ、と思いました(笑)」
文化庁から支援を受けて1年間アメリカで映画の勉強をしに留学されていたとか。
「向こうでは主に映画をプロデュースすることについて学びました。企画を立ち上げることとか、脚本を書くとか、お金がない中でどうやってそういうことをやっていくかということに興味があったんです。ニューヨークでプロデューサーをしている日本人の方にお世話になったんですが、日本とアメリカでは映画作りに対する考え方がまったく違うんです。ニューヨークのインディぺンデント映画に出資しようとする人たちは投資と考えているんです。だから純粋に監督や企画や脚本に対してお金を出そうって話になるんですが、日本だとそうはならないで監督や企画や脚本が中心から外れてしまい、何が中心で誰が責任を持つのかが曖昧になってしまう映画がたくさんある。ニューヨークで僕がついていた人は尖がった映画をプロデュースする人だったので、監督や脚本をすごく尊重してましたし、出資者ではなくあくまでプロデューサーが権利を持つことで責任の所在をはっきりさせていました。」
今後はプロデュースも手がけたいと?
「もちろんピンク映画だけじゃなく一般映画も作っていきたいなとは思っているんですが、まっていても仕事はそうそう来ないので自分で動いてやらなきゃと思って。運良く企画が通っても、進めていく過程でさっきお話したように変わっていってしまうこともあるじゃないですか。企画に合わせてやり方を変えていくのが理想なので、そういう意味でも映画のプロデュースという部分が自分の中にも身についていた方が、より撮りたいものを撮っていくために必要だと思いますね。
これまではピンクをやるので精一杯で、企画をいただいて、その企画のために自ら動くことってなかったんですけど、今回の留学はピンク映画の監督として行かせてもらっていたので、できれば来年の春先に一本ピンク映画をガッツリやりたいですね。その後は、ピンクもやりつつ一般映画にむけての動きもやりたいですね。僕は学生時代にずっとピンク映画が好きで見ていたので、自分にとってのピンクは「何でもあり」なんですよね。大体が3本立てなので他とはちょっと違うものがそのなかに入っていた方がお客さんも飽きなくていいだろうと思うんです。たまには太った人が主役でもいいだろうとか。」
この後、またガラッと変わった主人公たちの心の機微を捉えた秀作『ビタースイート』が同じくポレポレ東中野で公開されます。
「脚本家が違うと映画もぜんぜん変わります(笑)。『ビタースイート』はもともと脚本が出来てたんです。自分がもし企画から関わっていたら、幅が狭い人間なのでもっと2本の差も狭くなってたと思うんですが。脚本を自分で書かないのは、自分だったら思いつかないようなことを脚本家の方が書いてきてくださって、それを演出するっていうのが単純に楽しいです。自分一人から出てくるものって限界があると思うので、誰かと一緒にやるほうが刺激を受けて、それを上手い具合に映画していきたいですね。自分がそこで受けた刺激を見た人にも同じように感じてもらえればいいなぁと思います。」
執筆者
kaori WATANO