オムニバス映画『穴』:ジョー・ダンテ経由のブニュエル+デビット・リンチテイスト?佐々木浩久監督インタビュー
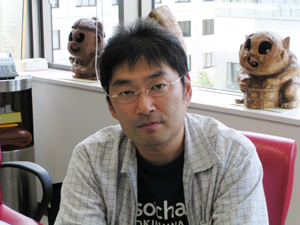
麻生学、佐々木浩久、山口雄大、本田隆一。この4人の映画監督が“穴”をテーマに四者四様の発想によって作り上げたオムニバス短編映画『穴』。それぞれ主演には尾美としのり、板尾創路、藤井尚之といったこれまたバラエティに富んだキャスト陣も話題となっている。なかでも佐々木浩久監督「胸に開いた底なしの穴」は、主演に“佐々木映画の看板女優”三輪ひとみを配し、まさに万全の態勢で挑んだ本格的ホラー。「長編ではなく短編でしかやれない、僕が思う三輪ひとみの魅力を追求することに専念した作品。」と佐々木監督自身語る。







—— はじめに”穴”というテーマをきいてどう思いました?
佐々木「穴をテーマにした映画っていうのは今までにも色々ありますよね。ジャック・ベッケルだとか台湾映画の『Hole』とかそのへんのものを思い出しました。物理的に穴というものを出してきて映像化しているのは『マルコヴィッチの穴』とかありますね。このお話をいただいた時、他の監督さんが誰で何人かなどは知りませんでしたが、具体的に穴を絵でみせるよりも、もっと広い意味で穴というものを見せていく方が面白くなるかな、と思いましたね。」
—— 4人の監督による連作ですがいかがですか?
佐々木「オムニバスって自分がこういうことをやってみたいな、って思っているものをやれる場という気がします。そういう風にして作る監督も多いんじゃないかな。1時間半のストーリーでは語りきれるものではなくて、でも語ってみたいもの。でもそれはなかなか商品にはならないものだったりするんですよね。だから短編映画を作るのは、自分が作りたいけどすぐには出せないものを20分間のなかでどうアプローチするか、そういうことを考えましたね。」
—— 長編では無理だけど短編つくりたいアイデアって結構たくさんあるんですか?
佐々木「そうですね。デビッド・リンチみたいなお化けが出てくるようなホラーじゃなくて不条理というか、お話自体が不思議で面白いものをやってみたいと思っていますね。」
—— 佐々木映画といえば女優は三輪ひとみ!ということで今回も三輪さんとのコンビですね。
佐々木「はい。やっぱりこういう話には彼女が合っていますね。短い話なので色んなことは語れないんですよ。彼女は出てきただけで色んなものを表現してくれる力を持っているんです。あまりキャラクターの薄い人だとその人がどういう人かを説明するためにシナリオで色々工夫していかなきゃいけないけど、短編映画にはそういう時間がないので、そこに三輪さんが出てきただけでなんかもう”妖しい”っていうか(笑)。一瞬にそういった世界観にぐっと引き込んでいくことができるんです。そこで三輪ひとみでいこうと思いました。それプラス三輪ひとみを撮るんだったら、どういう彼女が一番魅力的なのかということを表現してみたいなって。長編でそれだけを追求するのは難しいですけど、これも短編ならではできたことですね。」
—— 一番魅力的な三輪ひとみというとよく被虐性だとおっしゃっていますね。
佐々木「今回は巻き込まれて翻弄されてく主人公ですね。彼女は他の作品ではホラーで襲ったりするキャラクターも結構演じていますが、僕はそういうものよりやられる彼女の方が魅力的だと思いますね。もちろんそれだけじゃないですけど。」
——— 女子高生の扮装もありますが、意外に違和感ないですね。
佐々木「本人もそれなりに喜んで携帯で写真をとったりしていましたよ。ホームページにアップしたり。」
——— 主人公の姉の胸にある大きな痣がモチーフですけれどこのアイデアはどこから?
佐々木「川端康成の小説に「千羽鶴」というのがあって、増村保造が映画化もしているんですが、京マチ子さんが演じている父親の愛人だった人、彼女の胸に痣があって、子どもにとってはそれがすごく怖いという感情があるんです。例えば大きなほくろがあるとか、そういうのって口に出してはいけないことで子どもには恐ろしいもののように感じるんです。美しい女性の中にある醜い一部分というミスマッチさが恐怖として映る瞬間。そういうのを映像で表現してみようと思ったんです。」
——それはもしかしたら「四谷怪談」の岩に近いような美学でしょうか?
佐々木「いえ、お岩さんの方ははじめから怖がらせるってものでしょう?そうではなくこっちはもっと日常に潜んでいる恐怖です。あんまり見てはいけないものというか。夏にノースリーブの女の人の肩にそういう痣があったらあんまりジロジロみてはいけないと思うし。そういうものを嫌悪する気持ちがもちながらも自分にもそれはあるのかも、って女の子が思っているとしたらそれはすごく恐怖なんじゃないかと思いますよ。そういう心理的な気持ち悪さ、居心地悪さを”穴”というテーマとうまくあわせられると思いました。」
—— 今回はシリアスに仕上がっていますが、やはり随所に佐々木テイストが感じられました。能面みたいな顔でパンにバターを塗るお母さんとやたらヘンな顔でパンにかぶりつく姉さんだとか・・・
佐々木「ある現実ではない出来事として、だんだん普通の日常ではなくなってくる風景としてのシーンなんですよね。それが結果的にはちょっと笑ってしまう方向になってしまっているんでしょうかねぇ。最近ちょっとわからなくなってきてるんですよ。笑うつもりで撮ったんじゃないものが笑われたりするんで、そこは狙わないようにしようと思っているんですよ。そうしないとそのうちはずすんで(笑)。だから今回は笑いをとる気はまったくなしです。刑事まつりだったらそうしますけどね。」

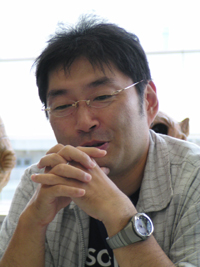



—— 外でのシーンは街並みがレトロっぽかったですね
佐々木「東大近くの根津の方で撮影しました。ロケハンにはすごくこだわって、今の町の風景じゃないようなところを探したんですよ。主人公が手に開いた穴をくぐりぬけたその先には昭和30年代の下町みたいな架空の一角にいってしまうような、そんな感じにしてみたかったんです。」
—— 三輪ひとみが穴の開いた“手”をみつける冒頭は、草むらで“耳”を見つけるデビット・リンチの『ブルー・ベルベット』みたいですね。
佐々木「あー、そうですねぇ。似てますね。でもあの映画は実際迷い込んだ世界はギャングがどうとかっていう割と単純な話でしたよね。まぁ、多少はありますね、最初のきっかけとしての部分はそうですよね。彼女はそこからどこか壊れた世界へ行ってしまうんですけれど。」
—— あとなんといっても、穴の開いた手のひらに這う蟻、あれはやはりルイス・ブニュエルからきてるんですか?
佐々木「それが、実はジョー・ダンテの『マチネー〜土曜の午後はキッスで始まる〜』という映画なんです。劇中で“マント”っていう蟻の怪物の映画が上映されるんですが、それの宣伝フィギュアとして置いてあったのがそのブニュエルの手のひらの蟻を意識したよなものだったんです。手のひらを這う蟻っていうのはこの映画を作った後に、「そういえばルイス・ブニュエルでやってたな」って思い出して、じゃあ『マチネー』のアレもブニュエルだったんだって思いなおしたんですよ。」
—— 劇中突然出てくる金髪の女性はどういう意味があるんですか?
佐々木「金髪の女性が日本人の住んでいるところにふっと出てくるというのは恐ろしい!という少年時代からの思いがあるんですよ。「ウルトラマン」や「ウルトラセブン」で金髪の女が出てくるとだいたい悪い奴なんですね。金髪の女性は、エロチックでありながら恐怖の存在として僕の中にあるんです。なぜそうなのかわからないんです。高橋洋は「戦争によって白人に辱められたその逆転現象だ!」なんて言っていますけどね(笑)。」
—— 最後に今後の活動を教えてください。特に発狂シリーズ第三弾は待望されていますが。
佐々木「今はテレビの仕事を結構やっていて、BS−iの「ケータイ刑事」シリーズに参加しています。テレビの仕事って主役の女の子が可愛くとれていれば、意外と自由でいろんなことができるんですね。そういうのをやりながらと、年に一本は自分が勝負できる作品を作れればと思います。今やりたいと思っている企画は、昔増村保造がやっていたような、谷崎潤一郎原作とかでちょっと文芸チックなホラーですね。テレビではできないものだし、エロチックというものを用いて人間の欲望が端的に表現したいです。それが結果的にホラーの形になるのかは分からないですけれど。
発狂シリーズは一応“人食い人種VS三輪ひとみ”みたいな方向性で決まっています(笑)。三輪ひとみがエマニュエル夫人みたいにタイのある田舎町にお嫁さんにいって、そこでの儀式のなかでやってはいけないことをやってしまって、大変なことになったので逃げて帰ってしまうと海を渡って東京に食人族がやってくる・・・みたいな展開です。プロデューサーも脚本家も監督もみんな忙しくてなかなか進まなくて・・・それに発狂シリーズってちょっと面白いっていうんじゃ没になるんです。よっぽど、人とは違う面白いものが出来ないとみんなGOサインが出ないんです。さっきお話ししたエロチックなものもやりたいし、発狂シリーズも進展させたいし、いずれにしてもライトなものじゃなくて作るとしたら映画でしかできないヘヴィなものにしたいですね。」
—— 面白いものを作るために忙しい合間にアイデアを練っているというところですかね。楽しみにしています!
執筆者
綿野かおり