行定監督と主演のつぐみに聞く 「贅沢な骨」は女を主人公にした男の子映画である。

奇妙な共同生活を送る2人の女と、女たちの屈託に巻きこまれていく男とーー。行定勲監督作品「贅沢な骨」は行き場のない男女の、少し怖くて、少し切ないラブ・ストーリーである。3人を演じるのは麻生久美子、つぐみ、永瀬正敏。恋の顛末は女性上位で動いていくものの、監督は「これは男の子映画です」。敢えて男性中心のスタッフで撮影し、“男から見たある女性たち”を描いた。先ごろのゆうばり国際ファンタスティック映画祭に出品し、客席から盛大な拍手で迎えられた本作品。会期中に行定監督と主演のつぐみさんをつかまえた。
※「贅沢な骨」は今夏テアトル新宿でレイトショー公開。

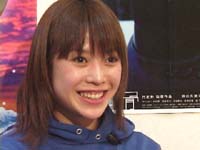



——「贅沢な骨」の発端は金魚の話だったとか。
行定 昨年の1月頃だったかな、紙1枚くらいの散文詩を書いたんです。ミキサーの中に金魚を飼っているっていう。それを、永瀬くんと麻生さんに見せて“これで映画、撮れないかな”って話になったんです。結果的にスタッフ、キャストとも誰ひとり欠けても撮れなかった作品になったと思います。スタンスとしてはプロが自主映画撮るみたいな感じですね。
——コールガールのミヤコと彼女と暮らすサキコ。2人とも屈託を抱えていますが、外へ向うものと、内へ向うものと表現方法が異なるため、正反対のタイプに思えます。
それぞれ麻生久美子さんとつぐみさんが演じるわけですが。
行定 2人の女性がいたらおしとやかな役をあてがわれるのが麻生さん。『贅沢な骨』では敢えてそうじゃないキャスティングをしてみたんです。つぐみさんとは僕が助監督をやった岩井俊二監督の『四月物語』のオーディションで初めて会ったんですけど、それ以来ずっと使いたいなと思っていて・・・。
つぐみ 私はこれまで麻生さんが演じたミヤコの方をあてがわれていた方の役者だったと思うんですよ。2人とも全然違うタイプの役を演ったんですね。
——撮影中のエピソードを教えてください。
行定 マンションに1週間くらいこもって撮影したんですけど、殆ど眠れなかったんです。ある時、すっごくシリアスなシーンを撮っていてですね…。つぐみさん、寝ちゃったんです。
つぐみ 言われると思った(笑)。結局、カットされちゃったんですけど麻生さんが眠っている私の唇を触るシーンがあったんです。触られたことに寝ながら反応していて…(笑)。ラッシュ見て、ものすごく恥ずかしかった(笑)。
行定 別のシーンは残っていますよ。寝ぼけながら喋っている。ラスト近くでうつぶせからあおむけに姿勢を変えて人形を持って喋るという、動き付きのシーンがあったんですよ。これもシリアスないいシーンだったのに(笑)、本当に寝ながら喋ってるんです。
つぐみ 終わったことすら覚えてないんです(笑)。ごめんなさい。




——永瀬さん、麻生さんとの共演はいかがでしたか。
つぐみ うーん(笑)、実を言うと自分のことで一杯一杯だったんですよ。目の前のことしか見えてなくて、監督にも相談ばかりしてました。
行定 相談っていっても、彼女の中ではきちんと形が見えてましたけどね。
つぐみ サキコってこうなんですよね、こう演っていいんですよね、って思ったことはどんどん監督に話すような感じ。
——女性2人が1人の男性を共有し、同じ部屋で関係を結ぶ。現実的には
非常に考えたくないシチュエーションなんですけど。
行定 実を言いますと現実にこういう女性たちを知っていたんです。これ、僕はよく言うんですけど、自分の中にあった原風景を映画にしてるんです。自分の感情としてわからない世界は表現できない。ラブストーリーだと特にそうなりますね。ミヤコとサキコのような女性たちというのは怖いんですけどね、傍にいる男は傷つきますから。でも、ものすごく印象に残る存在なんです。
——麻生さん演じるミヤコはサキコに対して何らかの愛情がある?
行定 いうなればプラトニックなレズビアン。男との仲を見せつけてヤキモチを焼かせようともするし、同じ男をあてがったりもする。ミヤコはサキコに純粋な気持ちがあったんだけど、それが行き過ぎちゃったんです。行き過ぎて悪意に変わってしまっても気がつかない。哀れなんです。周りは離れていくのにどんどん暴走していく。純粋さの裏の悪意、みたいなのがこの関係で表現したかったことかな。



——実際のつぐみさんはどちらのタイプに近いのでしょう。
つぐみ うーん、両方わかる感じがするんですよ。サキコも、ミヤコも、細かな要素は両方持ってるんじゃないかな。
行定 そう。この作品を何度か上映して、感想を聞くと両方わかるという声が多かった。“自分を分裂させ、2人になったみたい”とかね。僕は男なんで分裂させてるとは思わなかった。でも、同じ女性がある場面ではミヤコになったり、サキコになったり、逆転したりもしてると思うんですよ。実際、映画の後半は逆転してますしね。
——そして、迎えるひとつの死。
行定 “行定がまた殺したか”と言われそうですけどね。以前、ある評論で僕の映画は“死をファッショナブルに捉えがち”と書かれ、びっくりしたことがあるんです。そんなこと考えたこともなかったから。さっきの原風景とも言えるんですけど、僕は身近な人の死に何度も遭遇してるんです。昨日まで会ってた友達が突然亡くなるという体験に。これまでの作品にも死は出てきますが、実際に死ぬシーンはひとつもないんですね。僕にとって、死というのはすごくあっけないものだったから。あまりに突然訪れるもの、という気がしているんです。
#——行定作品は女性の視点が主体になっていますよね。
行定 僕は男のキャラクターでは走れないですね、愛情が湧かないんですよ(笑)。男を描くと全部自分になってしまう。女の人の気持ちはわからないですから、女優さんの持っている経験値や感情が一番の頼りなんですけど。今回、麻生さんはファムファタル的な存在感をミヤコの中に吹きこんだ。つぐみさんはつぐみさんで観客が知ってるような、どこかにいそうな女性を作り上げた。僕が現実に見てきた女性のイメージを持ちこんで、女優さんと話しこむと、ある時、“わかった!”って声があがるんです。今回のつぐみさんもそうだったんですけど。
つぐみ 私、何か言いましたっけ?
行定 言ったよ。撮影の3日目くらいになって….。
つぐみ ああ、“この子って観客に嫌われるタイプの子なんだな”って(笑)。
行定 サキコはボーイッシュで感情を閉じている、でも、ある種すごく大胆なところもあって女性からすると非常にいやなタイプなんですよね。つぐみさんからそういう意見をもらって、僕の望んでいた方向に行ったな、って思ったんです。
——主人公は女性、でもスタッフは殆どが男性だったとか。
行定 男から見た女性の映画にしたかったんです。メイクとか衣裳とか、通常女性が多い職種ですが敢えて男性にお願いした。女の子が主役だけど、これ、男の子映画なんですよ。
執筆者
寺島まりこ