大きな転換期を迎えたCO2(シネアスト・オーガニゼーション大阪)、第7回大阪アジアン映画祭【インディ・フォーラム部門】として3月10日より開催!
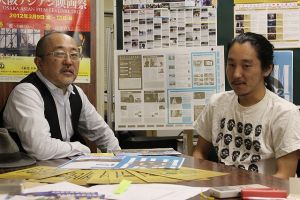
今年度から大阪アジアン映画祭の【インディ・フォーラム部門】となったCO2(シネアスト・オーガニゼーション大阪)。アジア諸国の監督たちを招いて行うシンポジウム<アジアン・ミーティング>とリンクしたことで、どういった変化を目指しているのか。本格始動したワークショップの目的とは。そして、今年度の助成監督3名の実感とは?
3月10日から行われる【インディ・フォーラム部門】上映を目前に控え、CO2事務局長と上映ディレクター、助成監督たちに緊急インタビューを行った。



第1回:CO2事務局長の富岡邦彦氏&大阪アジアン映画祭【インディ・フォーラム部門】上映ディレクター高倉雅昭氏インタビュー
——————————————————————————————
■【CO2】から大阪アジアン映画祭の【インディ・フォーラム部門】へ
——————————————————————————————
——CO2事務局長が富岡さんに替わって2年目ですが、去年と大きく違う点について教えてください。
富岡:大阪アジアン映画祭の実行委員会とCO2実行委員会がひとつになったという事ですね。
僕は大阪アジアン映画祭では<アジアン・ミーティング>を担当しているのと、CO2は第1回めと2回め、ブランクがあって去年の7回めから復帰して担当しています。今年から大阪アジアン映画祭とCO2を完全に一体化するにあたって、CO2は【インディ・フォーラム部門】という名称になりました。大阪アジアン映画祭に元々あった【特別招待作品部門】【コンペティション部門】【特集部門】に加えて4本めの柱になった訳です。
——【インディ・フォーラム部門】の内容は、どういったものですか。
富岡:シンポジウムの<アジアン・ミーティング>、アジアからの招待作品4本を上映する<海外インディペンデント作品>部門にCO2の助成作品3本をぶつけます。あとは<CO2ワークショップ短編作品集>として、CO2に係った監督とワークショップ生で制作した約40分の短編作品を3本。“夏休みこども映画教室”で子どもたちが制作した約4〜7分の作品2本を上映します。
——————————————————————————————
■対決!アジアの女性監督VS CO2助成監督
——————————————————————————————
——<アジアン・ミーティング>の役割をどうお考えですか。
富岡:<アジアン・ミーティング>は、元々3、4人のアジアの監督を呼んで上映とシンポジウムをするといったものです。海外に出ている監督たちは、作品で何を伝えたいのか明確な意図の元に、それぞれの国の社会状況を反映して作っています。作品そのものも、プレゼン能力も違ってるんですね。ドメスティックな日本のインディペンデント映画は、いい作品があってもそういった意識が低いんですよ。
今まではアジアの監督がメインで、ホスト側の監督として海外映画祭も経験している松井良彦監督や瀬々敬久監督、青山真治監督といった面々を招待してやってきました。ただ、アジアの監督をメインにシンポジウムをやっても、若い制作者に広がりがない訳です。そこに日本のインディペンデントの監督たちを入れて刺激を与えたいという思いがあったし、今回は今回は助成監督3人とアジアの監督3人でシンポジウムをやることで、そういった役割を果たせると思っています。
——アジアの監督はどういった方を選んでいますか。
富岡:例えば去年のリー・ホンチー監督だとロカルノ映画祭で金豹賞を獲っていて、ヒットはしていなくても海外の映画祭で評価されている監督です。今年の『オクスハイド2』のリュウ・ジャイン監督もそうですね。CO2の助成監督たちが外国の作品をどう観るのか。逆に今回招待したアジアの女性の監督たちがCO2の作品をどう観るのかということですね。
高倉:毎回CO2の作品だけの上映展で始まるから、今回日本の監督にとっては結構ショッキングだと思いますよ。
富岡:初期のCO2では割合そういったことをやっていて、1回目には『子猫をお願い』のチョン・ジェウン監督の1本目の短編と黒沢清監督の短編を上映したし、去年は柴田剛監督の『ギ・あいうえおス -ずばぬけたかえうた-』や、ジャン・ツーユー監督の『梨の女』を上映しました。CO2はどうしても作った仲間同士の盛り上がりになってしまうから、それを壊したいというのがあります。
高倉:いい刺激になるといいんですけど。
富岡:アジアでこんな作品があって、どう対抗するのかって視点で見てほしいね。CO2での制作体制はプロっぽくなっていて、制作部がいて各技術部がいて、と部署分けがあるけど、これも良し悪しだよね。映画はいくらでも自由に作れるんだから。
高倉:去年CO2上映展ディレクターの板倉さんが『ギ・…』を入れたのはそういうのがないって所で。
——見たことのない部署がたくさん出てくるって言ってましたね。
高倉:全員出演者とかぶってるっていうのもありますけど。
富岡:僕がさっきから言ってることと矛盾してるかもしれないけど、脚本がなくてもいいんですよ(笑)。ゴダールが“なんで脚本を提出しないといけないんだ”ってプロデューサーと揉めたりするけど、説得力の問題。柴田に脚本書かせても、どうせ脚本どおり撮らないんだけど、脱線しても面白いところに落とすんだろうって分かっている。そこは信頼関係しかないんですよ。
高倉:ギリギリでしたけどね(笑)。
——先日スタッフの座談会で、富岡さんが邦画と洋画の区分けは馬鹿馬鹿しいって話をされてましたが、今回は同じ土俵に乗る訳ですね。
高倉:一応分けてはいますけどね(笑)。今後、外国枠の本数が増えてそこに日本の作品も入ってくるといいなと思います。
——————————————————————————————
■CO2のワークショップが目指すもの
——————————————————————————————
——昨年との違いというとワークショップを本格的に開始したというのも大きいですね。
富岡:ワークショップは前年度もテストで無料で実施したんですよ。CO2の開始当時から感じていたのは、監督は助成金が出るってことで募集すれば、日本中から集まって来る。でも大阪市の事業として考えたときに、関西圏で大阪を行き来できる人達がどれだけ映画にリンクして、役者、スタッフとして育っていくのがCO2のプロジェクトのキモになるんですよ。そこを重点的にバックアップするために今年度から有料のワークショップを始動しました。予算が厳しいので赤字になりましたが、そっちに力を入れていかないことには。デジタル機材の普及で映画制作の敷居が低くなって、撮る人は増えたけど作品の質の低下は明らかです。今注目されていて頭抜け出して来そうな人材よりも、ワークショップでこれから撮ろうとしている人達を育てて行きたいですね。今年度ワークショップで学んだ人が来年度の助成監督やスタッフとして担っていってくれたらベストです。
——ワークショップの成果はありましたか?
富岡:今年度は役者の育成に力を入れたことで、それぞれの助成作品に前年度よりワークショップ生の出演者が増えていますね。もちろんやり切れてないところはたくさんありますが、出たい人と作りたい人をきっちり育てていく。来年、再来年くらいに成果が出るといいと思います。
——ワークショップで見えた課題はどんなことですか。
富岡:ワークショップの軸を明確にして行きたかったというのはありますね。何を柱に話をしていくのか。共通認識の部分ですよ。好き嫌いではなしに、あることを訴えるためにこのカットが間違っているのか、正しいのか。
今年後、最後のワークショップでリュミエール兄弟に習って1分間FIXで映像を撮りましたけど、あれは効果的だったね。元々あったアイディアに何を足すと面白くなっていくのか、誰が見ても明確です。それができた上での好きか嫌いか。最低限の技術の部分です。今映画制作を教えているところで一番の問題は、好きなようにやらせ過ぎってことです。何を最終目標にするのか、どういう話でどういう画を組み立てればこうなるという認識を、スタッフ、俳優さん全員が持ってないとダメなんですよ。
——今年度はそこまで出来なかったということですか。
富岡:出来なかったね。シネアストは映画を作る人のことで、監督だけではないんです。みなさん誤解して監督をイメージするし、これまでのCO2は監督中心で好きなことが出来るという風に思われているかもしれません。でも、前作の参考作品があって、次はこういう企画でやりますってことだから、次の1歩を踏み出してもらわないと。
一般のお客さんに観てもらえる形にしていくために、どんなやり方をすべきかという対話は必要です。助成監督たちはCO2で撮れるとなった時に、自分が考えていた最終的な落し所を見失うことが多いんですよ。もちろんそういったものを、壊したい人がいてもいい。分かった上で壊さないとダメなんですよ。
——来年度のワークショップでは、最初に1分間FIX映像をやるとよさそうですね。
富岡:理解が全然違うだろうね。
——関西圏ではスタッフ、俳優の横のつながりが希薄といわれていますが、それは何故ですか?
富岡:どうしても自主でやるとなると身近なところからスタッフを集めるし、各学校にはそれぞれのやり方があるため、交流はない訳です。もう少しそれぞれのいい部分が重なり合って競争心が出れば面白いだろうし、ニュートラルな場所としてCO2はあるべきだと思います。
昔は日本大学と大阪芸術大学くらいしか映画制作を教える学校はなかったんです。その後ビジュアルアーツ専門学校、映画美学校などの専門学校ができて。それ以外にも、東京芸術大学、関西では宝塚大学(旧・宝塚造形芸術大学)、神戸芸術工科大学と、そういった授業のある大学も増えています。それぞれの学校で利益の追求もある訳で、各学校で作った映画を並べてどっちがいいかってことは中々できないよね。昔から学生映画祭がないことはないけど…。シネ・ドライヴが元々そういう考え方で、ぶつかる場、交流の場を目指してたんですよ。あの作品でよかったあの人をここで使おう、とつながりが出来てきたら作品の質の向上になるからね。
——————————————————————————————
■インディーズ映画花ざかりの春の関西とCO2の今後
——————————————————————————————
——3月から4月にかけて関西では大量のインディーズ映画の上映がありますね。
富岡:アジアのメジャー系の作品もあるし、【インディ・フォーラム部門】もあるしシネ・ドライヴ2012もある。この次期に普通のお客さんに見てもらって点を付けて欲しいよね。
高倉:全部観るのは大変ですよ(笑)。できたら2年事業にしたいですね。
——事業のスパンとして無理ですか?
富岡:単年の事業で始まっているから、橋下徹大阪市長がどういう組み換えをしていくのか分からないけど2年の事業が理想だよね。上映展が決まる時期に次の監督が発表になると、ワークショップ生もたくさん集まるだろうし準備期間が長く取れる。
高倉:かぶせて行く状態になれたら一番いいんですけどね。
執筆者
デューイ松田
関連記事&リンク
第7回大阪アジアン映画祭:インディ・フォーラム部門スケジュール
第8回シネアスト・オーガニゼーション大阪
シネ・ドライブ2012