『怪談新耳袋 怪奇』『東京島』というまったくジャンルの違う2本の作品が公開される篠崎誠監督にインタビュー!!

本当にあった怪談話を集めた原作「新耳袋」を映像化、BS-TBSで100話以上にも及ぶオムニバスで、観る人を恐怖のどん底に突き落としてきた「怪談新耳袋」が、遂に、劇場版『怪談新耳袋 怪奇』として復活!!(「ツキモノ」と「ノゾミ」のオムニバスストーリー)。過去の劇場版はいずれも大ヒットを記録し、多くのファンから次回作が待ち望まれていた中、4年ぶりにして怪談新耳袋史上最大の恐怖が襲いかかる。
今回、最大の話題は映画初主演の真野恵里菜。ハロー!プロジェクト所属で、歌手やTV、舞台、CM、雑誌など多方面で大活躍中であり、言わずと知れた人気NO.1アイドルが、初主演にして「ツキモノ」と「ノゾミ」で2役を熱演。まったく異なるタイプの作品で違うキャラクターを見事に演じ、さらには、主題歌も真野本人が歌い、英語歌詞にも挑戦する。
一方、『東京島』は直木賞作家・桐野夏生のスキャンダラスなベストセラー小説を映画化した現代人のサバイバル・エンタテインメント。桐野夏生の原作は、若さに満ち溢れた男たちと40代の女がひとり、無人島に流れ着くという逆ハーレム状態の設定がセンセーショナルな話題を呼び、ベストセラーを記録。極限状態の人間のダークな欲望を描いた原作を、映画版では生への希望に満ちたサバイバル・エンタテインメント作品に昇華させている。
『おかえり』(96)でベルリン映画祭最優秀新人監督賞はじめ、多数の映画賞を受賞し、話題をさらった篠崎誠監督だが、このたび『怪談新耳袋 怪奇』『東京島』とまったくタイプの異なる異なる2本の新作が公開されることになった。今回は勢いにのる篠崎監督にお話を伺うことにしよう。



–篠崎監督の著作やトークショーなどでもホラーに関する博識ぶりは存じ上げておりましたが、今までホラーを撮っていなかったというのは驚きでした。
「そうですね。自主製作ではホラー映画をいくつも作りましたが、商業映画では初めてになります」
–どうしてやらなかったんですか?
「それは僕に聞かないでください(笑)。単純にプロデューサーの方々から声がかからなかっただけです。実際に『新耳』のプロデューサーにも、ずっとやらせてくれと言い続けていたんですけど、最終99話まで終わってしまって…。もうこうなったら、いっそ実話ホラーだけは撮らないと心ひそかに誓いをたてたほどです(笑)。そうしたら、この話をいただいたということなんです」
–まさに待ちに待ったという感じですね。
「ええ。しかも脚本は三宅隆太くんだというので、あっさりと誓いを反故にしました(笑)。ただ若干、『東京島』の仕上げが伸びてしまったんで、『新耳』の準備と重なってしまったのが大変でしたが」
–ということは『東京島』の撮影が先に終わったということですか。
「そうです。『東京島』が去年の11月撮影で今年の3月の終わりに完成。『新耳』は今年の3月後半に撮影で4月の終わりに完成しました」
–『新耳』『東京島』両作とも女性が主人公の映画ということになりますが、少しだけ『東京島』のお話を聞かせてください。木村さんはどんな女優さんなのでしょうか?
「一度木村さんと仕事をした人はみんな彼女のことを褒めるのですが、その理由がよくわかりました。自分の芝居だけじゃなくて、自分が関わっている映画そのものが少しでもよくなるにはどうしたらいいかを一緒に考えてくれる方ですね。すごく謙虚で、スタッフに対しても、新人の俳優に対しても、同じように気をつかって接してくれるし。とても仕事がやりやすかったです。木村さんは、本来『ぐるりのこと。』を観てもわかるように、単にうまい演技をするというよりも、本物の感情をリアルに宿して、登場人物に命を吹き込む
ことのできる人だと思います。ただし今回の『東京島』の主人公である清子という役はナチュラルに演じるだけでは成立しない役です。弾ける部分も必要で、状況によって、玉虫色に自分を変化させ続けるヒロインです。そういう意味では、頭の中だけで役を掴むのが非常に難しい役だったと思います。撮影の準備期間中に、木村さんから「原作は読んだ方がいいでしょうか」という質問を受けました。正直に「脚本とはたいぶテイストが違うので、戸惑われる部分もあるかもしれないですが、是非読んでください」とお願いしました。そして「読んだ上で忘れてください」と言いました。忘れてください、と言っても忘れられないくらい強烈な原作ですが、つまり、原作を蔑ろにするんじゃなく、しっかりと読んだ上でそれを踏まえて、原作とは違う、木村さんにしかできない清子を演じてほしかったんです。映画全体のカラーは原作とは大分違いますが、実はほぼ同時に別の会社も映画化に名乗りをあげていて、そちらもキャストや監督、公開規模も決めた上で、詳細なプロットもでき上がっていたようです。その上で桐野さんご自身が、僕らのプロットの方を気に入ってくださって、映画化の許可がおりたんです。
公開規模やレイティングも含めて、原作よりもかなり表現を柔らかくせざるをえなかったのですが、ひとりの女性が無人島という場所に来たおかげで、都会の生活では決して見えなかった新しい自分を次々と発見、獲得していくという根幹の部分だけはぶれないようにしたいと思いました。僕自身もシナリオは当然のこと、原作自体も何度も何度も読み返しました。それでもまだ掴めないところがあったのですが、今回並々ならぬお世話になった徳之島と沖永良部島の二つの島を実際に歩いてみて、ようやく肌で実感することが出来きました。ですから唯一木村さんにお願いしたのは、あまり役作りをガチガチに固めてしまうのではなく、実際に島に入ってから海や風を肌で感じた感触を大事にしてもらいたいということでした」
–『東京島』を篠崎監督が撮ると聞いて意外に思いました。
「それは僕も意外でした(笑)。実はプロデューサーの一人である森恭一さんとここ1年ほど、別な企画を練っていたのですが、今実現するにはちょっと難しいということになってペンディングになったところでした。その直後に相談したいことがあると言われたのが『東京島』だったんです。
このときロングプロットも出来あがっていて、原作と一緒にそれを渡されました。そのときに言われたのが、原作のテイストを忠実に再現するのではなく、わたしたちが映画のテイストとして考えているのはあくまでロングプロットの方だと。だから二つを読んだ上で話しをしたいと言われました。確かにロングプロットはロングプロットで面白かったです。ただ原作とはテイストが違っているので、そこで完全にロングプロットの要素だけでやるか、それとも原作にあった要素をもう少し戻すことは可能なのかというやりとりをしました。話し合いを重ねて、半年くらいかけてシナリオを完成稿まで持っていったという感じですね」
–この映画をやりたいと思った決め手は何だったんでしょうか?
「やはり清子というキャラクターが面白かったということですね。ちょっと今までにないような不思議な感触の映画になると思いました。ゴールディングの『蝿の王』のような権力闘争とかサバイバル映画とも違うし、『太平洋の地獄』や『キャスタウェイ』のような孤島からの脱出物とも違う、ジャンル分けできないような映画。ただし全国公開を目指すということで、さきほども言いましたが、原作にあったような過激な性描写は出来ない。いや、出来ないというよりも、そもそも、この映画の企画立案者である鈴木律子さんやプロデューサーの森さんや吉村さんも、そこの部分に惚れこんで映画化を狙ったのではなかったんです。ある種、大人向けのファンタジーというか、これまでにない感触の新しい女性映画にしたいと。スキャンダラスさを武器にとんがった映画にするのではなく、できるだけ幅広い層に受け入れられるようなエンタテインメントを目指したいと。それはすごく冒険だし、僕も面白いんじゃないかなと思ったんですね。そういう意味でも、自分の色はこうだと決めない方がいいと僕は思っているんです。そうしないと自分がどんどん小さくなってしまいますからね」
–今までの篠崎作品と傾向が違うように思ったのですが、大変だったところはなかったんですか?
「さきほども言いましたが、脚本は僕自身が書いていませんし、僕自身はしょせん男ですから掴みきれない部分がありました。シナリオは当然のことながら何度も読み、実は原作本も木村さんには「読んで忘れてください」と言いながら(笑)、自分自身は忘れるどころか撮影に入っても読み返しました。間違いなくこれまで生きてきて、一番読み返した小説です。当たり前のことですが、あらゆる優れた小説がそうであるように、桐野さんの原作にも無駄な文章なんて1行もないわけですよ。これしかない、という書き方をされている。すごく映像が浮かぶ書き方なんですが、実は活字ならでは、小説ならではの表現であって、それをそのまま映像に置き換えることは不可能なんです。でも、いろんな事情で割愛せざるをえなかったある1行なり、2行なりを映画の別の部分になんとかエッセンスとして活かせないものかと思っていろいろ考えました。今も手元にある原作のハードカバーは海を何度も渡って潮風にあたってボロボロですね」
–島での撮影も大変だったのではないかと思うのですが。
「自然相手ですからね。ぼくよりもスタッフが大変だったんじゃないかと思います。海で大変だったのは潮の満ち干きがあることですよね。この日はあと2時間で海が見えなくなります、とかそういうことがあるので、海のシーンの絵コンテを書いて、カットごとに計算して。こことここのカットは朝11時からとか、この後は翌日になりますといった具合に、チーフ助監督の久保さんが中心になって、メインスタッフが全員集まって作戦会議をしました。
撮影は99%が島の中なので、わき目をふるような余裕が何もなかったんですよ。今まで、これほど映画のことだけ集中していられた現場はなかったですね。そういう意味では贅沢な現場でした。テレビも天気予報だけしかみませんでした。ただその天気予報も、島の反対側とではまったく違うので、途中からは天気予報でさえ見なくなって。実際に行って、どうするか考える。いかだ船を出すところでも、スタッフが水浸しになっているから、ぼく一緒になって何時間もずっと海に浸かりながら撮影をしていました。足の皮なんかもふやけてベロリとめくれましたけど(笑)。本当に俳優もスタッフもがんばってくれました」
–『東京島』の見どころを教えてください。
「こういうヒロインってなかなかないと思うんですね。男性が脚本を書くと、分かりやすい女性像になりがちだと思うんです。悪女か娼婦か、それとも聖女か無垢な少女か、そうでなければ母親。いろいろなものを抱えつつ、全部に染まらないのが清子さんなので、それを楽しんでいただけるといいですね。木村さんのはつらつとした芝居を楽しんでいただけたらいいなと思います。是非、プロデューサーの方々には木村さんにどんどんそういう役をオファーして欲しいですね」
–薄幸な役ばかりでなくということですね。
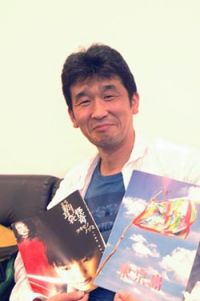
–それでは『新耳』のお話を聞かせてください。この作品に主演されている真野さんはどういう方だったのでしょうか。
「真野さんは三宅くんが脚本を書いているテレビドラマ『東京少女』に出ているのを事前に見せていただいて、とてもいいなと思いました。いわゆる作りこみすぎた芝居ではなくて、相手の役者の芝居に自分の感情を合わせることが出来る人だなと。これはホラー映画に限らずなんですが、俳優さんはその人が持っている雰囲気とかたたずまいがとても大切で。ちょっと誤解を呼ぶかも知れませんが、スクリーンに映るのは演技のうまい下手をこえたこの人の人柄なんじゃないかって気がするんです。極端に言うと、演技をしていないときにどんな表情で人の話を聞いているか、どういう風に立っているかということがぼくにとっては重要なんです。真野さんは大丈夫だなと思いました。それは『東京島』の木村さんも同じでした」
–本当にやりやすい女優さんだったという。
「そうですね。「ノゾミ」「ツキモノ」の2本とも独立した話で、違うキャラクターなんですけど、心の中では陰を抱えているというところは共通していますね。「ツキモノ」編ではキャーキャー悲鳴を上げてもらったんですけど、「ノゾミ」編の方はお化けを見ても息をのむような違いを出したいと言ってきてくれて、やってもらいました」
–「ツキモノ」編では逃げ惑う大学生エキストラの数が多かったですね。非常に豊かな画面だったと思ったのですが。
「『新耳』史上、もっともエキストラが多かったらしいですから。脚本の三宅くんが講師をしている東京工芸大学の学生たちと僕が関わっている立教大学の映像身体学科の学生諸君が無償で参加してくれたんです(笑)。その代わり、『○○大学のみなさん』ではなくて全員の名前をクレジットに入れてくださいプロデューサーにお願いしたんです。それを了承していただいたので、良かったですけどね。リハーサルも何度もやりましたし、本気で逃げ回ってもらいましたね。エキストラの学生たちはよく頑張ってくれましたよ」
–今後、ホラーを撮っていきたいということは?
「お話さえいただければ、まだまだ試したいホラーの形というのは自分の中にあるんです。今度の映画でも様々な事情できかったアイデアがたくさんありますんで(笑)。でもTV用の『新耳』5分版の短編も2本やらせてもらえたので、本当に嬉しかったですね。中篇の『ツキモノ』『ノゾミ』があって、『東京島』があって。その間に北野武さんの最新短編の助監督もやりました」
–そうなんですか? 篠崎監督が助監督なんて贅沢な現場ですね。
「カルティエ財団が今パリで大規模な北野武さんの展覧会を開いているのですが、その展覧会の中だけで上映するために作った数分の短編なんです。題名が『これが日本だ!』。外国から観た間違った日本がテーマで、正式タイトルもあて字っぽく『是我日本陀!』にしました。TBSのスタジオにセットを2つ建てまして、1日で一気に撮影したんです。正直自分が監督する現場よりも緊張しました(笑)。日本家屋の室内に鳥居があったり、狛犬が並んでたり。畳の間なのになぜかど真ん中に風呂があって、庭先では力士がダッチワイフと相撲をとってたり(笑)。襖をあけるとその向こうが巨大な水槽になっていて、クジラが泳いでるんです。武さんが主演をかねて、社長の役なんですが、「あの、クジラを刺身にして食べたい!」って言いだしたり。もう無茶苦茶なんです。ダンカンさん、ガダルカナル・タカさん、グレート義太夫さん、浅草キッドの二人も出演していて。ちょうど、『アウトレイジ』の仕上げと並行する形で、北野監督と何度か打ち合わせをしまして。武さんが口頭で言ったことをメモに書いて、忘れないうちにある程度の形にして、それを読んでいただいて、修正する形でシナリオを作っていきました。それを編集してまた武さんに観ていただいて…。もともとサイレント映画の手法でやろうかというのが出発点だったのですが、結局、モノクロ・サイレントとカラー・トーキー版の2バージョンを作りまして、カラー・バージョンが採用されました」
–それは日本では観られないんでしょうか?
「いずれ展覧会そのものが日本でも開かれれば…」
–それは楽しみです。それでは最後に『新耳』の見どころを。
「この映画はお話がシンプルですし、とにかく若い人に観てもらいたいと思っているんですよ。僕も最近は大学生たちと付き合いがあるんですけども、地方から東京に出てきて、何となく友だちと付き合いがしづらいというような。自分の居場所がないなと思っている人たちにも観てもらいたいですね」
–そういう人たちは真野さんに共感しやすいでしょうね。
「それはやはり脚本を書いた三宅くんの力ですし、三宅君の脚本をきっちり読みこんで、それに応えた真野さんの力です。恐怖シーンを除いてもドラマとして成り立つようなものにしたかったというのはあります。もちろん怪談ですから、それと同時に怖がらせることもきちんとやりました。若い人にワーワーキャーキャー言っていただいて、楽しんで見ていただけたら嬉しいですね」
執筆者
壬生智裕