鬼才、実相寺昭雄監督の渾身の遺作『シルバー假面』の脚本家、中野貴雄ロングインタビュー

1971年から72年にTBS系列で放送された特撮シリーズ『シルバー仮面』が装いも新たに蘇った。奇しくも本作はオリジナル版を生み出した実相寺昭雄監督の遺作となってしまったわけだが、ヒーロー、怪人、エロス、光と影、そして江戸川乱歩など、これまでの実相寺作品のテイストが詰まった快作となっている。
実相寺監督の演出ノートには「シルバー仮面は、自由な精神に則った、また自由な変幻自在を身につけた、類まれなるヒーローなのである」とあったという。その言葉通り、今回の『シルバー假面』では、時代設定を大正時代に移し、主人公のシルバー仮面を女性にするという新たな設定が目を引く。森鴎外とドイツ女性の間に生まれたザビーネが、時空を越えた恐るべき怪人、カリガリ博士と対決する様子を全3話で描き出している。
今回は、本作の脚本を担当した中野貴雄氏に、『シルバー假面』制作の裏側と、実相寺監督について、たっぷりと話を聞いてきた。



■『シルバー假面』は時空を越えてさまようヒーローなんです
—中野さんにとっての『シルバー假面』とは何だったのでしょうか?
「正直言うと、70年代の『シルバー仮面』は僕の記憶からは薄れていたんですよ。それで今回、お話をいただいて改めてオリジナルを確認してみたんですけど、あれって撮影時期が秋冬なんですね。だから風景がすごく寂しくて(笑)。それと基本的に『シルバー仮面』は非定住型スーパーヒーローだったんですね。大抵のスーパーヒーローには、秘密基地があったりしますよね。それとか仲間がいたり、警備隊の人がいたりとかいった、ちゃんとしたアイデンティティがあるんですけど、『シルバー仮面』にはそういうのがないんですよ。そこが面白かったですね。
これは企画の当初から言われていたことなんですが、『シルバー仮面』というものは各時代ごとにいるんです。たとえば平安時代にだっているし、古代ローマにだっている。ひとつの時代のヒーローなのではなく、時空を超えてさすらうヒーローなんだと。それは時空だけでなく、国境であったり、昼と夜であったり、男性と女性という枠をも飛び越えるんです。あの甲冑さえあれば、あとは『シルバー仮面』という概念があるだけなんです。
70年代の『シルバー仮面』自体がアールデコ様式なんですよね。クライスラービルや、エンパイヤステートビルの展望台みたいなのが頭についているし、銀色で、アマチュアレスラーみたいな格好をしている。ちょっとメトロポリス的なところもありますし。20年代というのはココ・シャネルとか平塚らいてふとかが活躍した時代ですから。女性が冒険するというのも20年代っぽいじゃないですか。ロケッティアというイメージもあったし。だからこのアイディアもウルトラCだとは思わなかったですね。さすが実相寺さんだと思いましたね」
—本作の原案は、オリジナル版の脚本家である佐々木守さんと実相寺監督が担当しています。佐々木さんは残念ながら、06年の2月に亡くなられてしまったわけですが、作業はどのように進められたのでしょうか。
「これはいろいろと変遷があるんです。最初は現代ものにしようという案があったらしいんですけど、現代ものの仮面劇というのが実相寺さんの中でピンとこなかったらしいんですね。『オペラ座の怪人』とかもそうですが、そもそも仮面なんて大仰なものじゃないですか。そこで、時代劇になったらしいんですよ。
佐々木さんの原案には、1920年代を舞台に森鴎外の娘が活躍するという原型はありました。だからレールは敷いてあったんです。あとはそこに何を積もうが構わないという感じで。そこには実在の作家とか軍人なんかの名前がいっぱい出てきてました。僕は、野口雨情(うじょう)だの、石原莞爾(かんじ)だの、そういう人物を交通整理する役割でした」
—ベースになる佐々木さんのプロットというのは完成されていたんですか?
「とりあえずプロットという形ではなく、その一段前のシノプシス(あらすじ)という形でしたね。こういう人物が出てきて、といったブレインストーミングした結果をまとめた感じで。だから、話のキーになるようなものはなかったですが、すごく面白かったですよ。交通整理が全然されていない状態で話を終わらせる気ゼロといった感じですから。サトウハチローとか吉屋信子などいったいろんな人が出てきて。
あと今回、製作陣が几帳面だなと思ったのは、登場人物の遺族の方に一筆入れて、みんな許可をとっているんですよ。だから、軍人の名前とか女流作家の名前とかダメだろうなと思ったのは最初から変えてあるわけです」
—最初から大河ドラマ的なスケール感だったわけですか?
「そうですね。もっと先も考えていたみたいです。この先、満州に行っちゃうとか。『シルバー假面』の裏には、日本の近現代史をやりたかったみたいですよ。それくらいのスケールはあったみたいですよ。ゆくゆくは広がっていくんじゃないですかね。僕としては、終戦直後のとりあえず春日兄弟が生まれるところまでいくといいかな、と思っていたわけなんですよね。そしたら、1970年代のシルバー仮面につなげられるじゃないですか」
—水橋研二さんが演じる江戸川乱歩も最初から登場していたんですか?
「いや、江戸川乱歩の役はそんなに大きくなかったんですよ。最初は3つの話の中で、単に2番目のエピソードに出てくる人物に過ぎなかったんです。ただ元々、江戸川乱歩が覗き見するという、いわば『屋根裏の散歩者』みたいな感じは欲しかったんですよ。
そもそもこの作品というのは、話自体が覗きからくり風になっているんです。物語が入れ子状態になっているわけです。つまり、シルバー假面を演じている役者が舞台にいて、それがまた、1920年代の劇場の中で、それ自体が1920年代のコスチュームドラマを撮っているという。これは一種のパノラマなんです。そしてパノラマといえば、江戸川乱歩ですよね。そういう象徴でもあるわけです」
—今回、映画館や劇場が舞台になっているというのは非常に象徴的ですね。
「実相寺さんというのは、ウルトラマンのひかりの国を作ってきた人ですよね。その反対に怪獣墓場というのも作りましたよね。
だから今回お亡くなりになって、『ひかりの国に行ったんだよ』『いや、怪獣墓場に行ったんだよ』といろいろと言われているわけですが、僕はどっちにもいると思うんです。光でも影でもあるわけなんですよ。そして光と影がすごい速度でフリッカーを起こすところに実相寺さんの眼差しがあって。
それは要するに映画ということなんですよ。映画というのは光と影が連続して映し出されるものですよね。今回の『シルバー假面』にも象徴的なカットがたくさんあります。強烈な光が差しているカットもあれば、暗黒の奈落みたいなカットもある。それは今回の話のテーマなんじゃないでしょうか。光の象徴であるシルバー假面と、影の象徴である暗黒のカリガリ博士。この決着は永久につかないんです。光と影の永久の闘争がテーマなんで」


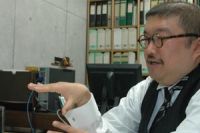
■カリガリ博士は僕の実相寺昭雄像なんです
—実相寺監督との脚本のやりとりはどんな感じだったんでしょうか。
「カリガリ博士を非常に気に入ってましたね。実はお話をいただいた時に、監督はこういうの好きなんじゃないかな、ということをちょっと入れたりしたんです。カリガリ博士って、人類が好きなのか嫌いなのかわからない人ですよね。文句ばっかり言ってるわりには楽しげだし。女の人の背中をなめちゃったりして、人生楽しんでいますよね。ポエティックな部分もあるし、エロティックだし。実はカリガリ博士はこっそり実相寺昭雄さんにあて書きしたんですよ。カリガリ博士は僕の実相寺昭雄像なんです」
—そうなんですか。
「人間に対して警告のようなものを発するじゃないですか。『人間とは愚かな生き物である。人を宗教や人種で差別する…』みたいなね。私は無差別に人を殺す、バババババッ(と人を撃つ)、みたいなね。ああいうのお好きかなと思って。僕も好きだし。世をすねているんだけど、俗世は絶ち切れない人物みたいな。それが実相寺さんの宇宙人像じゃないですかね。
例えばウルトラセブンに登場するメトロン星人って親切ですよね。別に人類に警告なんか与えなくてもいいのに。嫌味もいっぱい言うんだけど、最終的に人類のこと、すごく好きだし。
それと表現主義というのが実相寺さんの世界なんですよ。劇中にもありますが、『紙の月であっても、月に見える。見たいものしか見えないし、聞きたいものしか聞こえないのが人間だ』といったことをおっしゃるわけですね。あれも実は現場で足した台詞なんですよ。
実相寺さんのパートって実は5分長いんですよ。最初の脚本はタイトに40分くらいにまとめたんです。ただ、それを見て、『どうだろう…。直す!』といって持って帰ったあとの第2稿では、前よりもバーンと膨らんじゃって(笑)。
実相寺さんはスプラッターなイメージがお嫌いなんです。鋼鉄の処女とか拷問シーンとかは、具体的な血のりのイメージがするので、それよりはむしろ、光が人間を殺すとするために、レントゲンに置きかえられましたね。この年にレントゲンが発明されたはずだ、というのを随分調べてましたね。だから実相寺さんの筆もかなり入って、それによってディテールがどんどんアップしていきましたね。
基本的に実相寺さんの説明台詞って長いんですけど、あれはきっとああいうBGMなんです(笑)。だからおそらくあれって目くらまし的にいろんなディテールをバンバン撒いているんだと思うんですよね。時々、説明台詞が途中で舞台裏で聞こえてくるような、オフになることもありますし。
だから具体的な口上自体を理解しようとすると、複雑になると思うんですよ。それならむしろ感じた方がいいんですよ。ブルース・リーみたいですが。最初の寺田農さんの長台詞だって、どんどん増えていくんですよ。カリガリ博士の台詞もどんどん増えていって。ひとことふたこと僕が書いたものから派性される、たとえば千年王国であったりですとか、実相寺さんの宇宙にあるものがどんどん付け加えられていったりするんですよ」
—そういうことだったんですね。
「だから思ったんですけども、第2話に宇宙樹というものが出てくるんですけど、あれは宇宙に生えている樹、いわゆる北欧神話に出てくるユグドラシルというものなんです。それとシルバー仮面が持つニーベルンゲンの指輪なんかも、実はガジェット的に入れたものだったんですが、最終的には大きな意味を持ってしまったんですよね。
結局実相寺さん自身が大きな宇宙樹なんですよ。僕らは実相寺さんという宇宙樹を通じて、怪獣を知ったり、エロティシズムを知ったり、電車の世界なんかを知ったわけですよ。表面的には実相寺さんはいなくなったけど、精神の中には実相寺さんという大きな樹がドーンとあるわけですよ。だからこれは遺作ですけど、これは終わりじゃなくて、ここからが始まりなんですね。
—ではそれぞれの心に実相寺さん的なものが。
「そうですね。確かにこんなのシルバー假面じゃないという意見も聞くんですよ。春日兄弟も出てこないし。でも僕は思ったんですが、これはオリジナルなんですよ。70年代の『シルバー仮面』をさかのぼったエピソード1なんだと。今回は実相寺ワールドという宇宙樹の3枚の葉っぱを見ただけで。ここから『シルバー仮面』サーガというのは今、始まるんだと思います」
—それにしてもエピソード1というのは分かりやすいですね。
「そうなんですよね。本当は春日兄弟の先祖みたいな人を出そうと思ったんですが、計算するとまだ生まれたばっかりか、もしくは生まれる前くらいの世代の話になるんですよ。でも70年代版の子供たちの父親が、どこかの春日さんのお宅で生まれているはずなんですよ。今回はちょっと出せなかったんですけど、でも、もし『シルバー假面』を続けさせてもらえるならば、これが春日兄弟につながっていくわけなんですよ。
—『バットマン』『スター・ウォーズ』の例を出すまでもなく、最近のエピソード1的なものって、ラストが旧作につながるものが多いですもんね。
「そう。古い『シルバー仮面』を確認したら、いろいろ面白いことがあるんですね。実相寺さんが担当した回で、宇宙人が出てくるんですけども、その絵が劇中に図鑑としてすでに描いてあるんですよ。〇〇星人だ、といった感じで。するとこの図鑑を書いた人は誰だろう? と広がっていくわけですよ。南方熊楠? 柳田国男? とかね。実相寺さんがおっしゃってましたけども、まったく自由で制約のない。
あまり大きな声では言えませんが、今はいろいろおもちゃ屋さんのことなんかもちょっとは目くばせもしなくてはいけないんです。ちょっとカッコいい男の子を使って、ヒロインもお色気っぽくしてオタクの心をわし掴みにしよう、とか邪心が湧いてくるんです。でも本当はヒーローって、それがないから、純粋にヒーローなんですよね」



■ステレオタイプな悪人にはしたくなかった
—本当に自由に作品世界を作り上げたんですね。
「オリジナル版は、光子ロケットの設計図をめぐって、宇宙人と対決するという話なんです。そして、その光子ロケットが生まれる前の段階のものは、今回ネタふりをしているんですよ。光子というものが発見されたんだけども、それに気付いたのは、後にナチスになっていく人たちだというくだりで。後にこの人たちは人類に対する大きな犯罪を犯して、すごく恐ろしい存在になっていくわけなんですけども、まだこの段階ではそうではないんです。
ところで戦前と言うと、軍国主義が台頭した暗い時代のように思われがちですが、調べていくと、いろんな面白いことも出てくるんですよ。宝塚や野球が始まったりとか、12時になったら時報がわりに大砲を打ったりとか。浅草のオペラでもペラゴロという着飾った若者たちがいたりしたわけですが、それって今の渋谷と何も変わらないですよね。だから軍人をいばっているだけのステレオタイプなものにしたくなかったんです。この人たちが悪いから日本は軍国主義に向かっていった、みたいな。正義感で秩序を守りたいという、むしろいい人にしたかったんですよ」
—軍部の人たちはどことなくウルトラ警備隊っぽいですよね。
「そうですね。でもこの人たちはものすごい破壊をもたらしてしまうわけなんですよ。『善人は危険なものだ』とカリガリ博士が言うのはまさにそこなんですよ。善人は善人であるがゆえに徹底的に何かをやってしまうわけなんですね。
ヒトラー君も出てきますが、悪人にはしたくなかったんですよ。むしろオタクちっくな、純朴な礼儀正しい青年で。そういう善人が手のひらを返したら、悪人になってしまうという。実はカリガリ博士というのは一番愛すべき人物ですよね。一番陽気だし、いろいろ面白いことを言ってくれそうだし。この中で誰と一番一緒に酒を飲みに行きたいかというと、カリガリ博士ですよね。でも、実際は一番悪い人なんですよね。そういう善悪がころころ変わる表裏が1枚のコインになっているようにしたかったんです」
—実相寺監督が総監督となっていますが、具体的には何をされたんでしょうか?
「全体のトーンを決める役割ですね。3幕の舞台劇にしたいんだとおっしゃってました。舞台で始まり、舞台で終わりたいんだと。僕が『カリガリ博士』といったら、『それだ!』 『ニーベルンゲンの指輪』だといったら、『それだ!』といった感じで。ワーグナーのオペラのようなものを念頭に置いていたようですね。
あと、実相寺さんに限らず、製作会社のコダイの人たちにも共通していたのは、鋼鉄のイメージ、飛行船のイメージなどですね。実相寺さんが担当したのは、全体の色を決めたということですね。なおかつ大冒険活劇なんで、あまり深刻にならないようにもしました。みんな遠慮して笑わないけど、実は笑ってもらいたい部分がいっぱいあるんですよね」
—僕が観たときは笑いが多かったですよ。
「そういう風にしたかったんですよ。なおかつ時代のうねりみたいなのがあってね。どうしても今のヒーローというのは、精神の内面に向かいがちじゃないですか。ここにいていいんだろうか、みたいな内向型のヒーローが多いでしょ。でもそうじゃなくて、外向型のヒーローにしたかったんです。
いろいろな差し障りもあって、僕たちは近現代のヒーローを持ちづらいんですよ。どうしても軍部という問題も出てきちゃうし。そこの妙なこわばりを解きほぐしたかったんですね。もちろん実相寺さんは明確にそう言ったわけではないですけが。ただメイキング撮影の時に言ってたのが『戦前というのが特殊な時代なのではなくて、今と変わらないのだ』というね。
—そういうトーンを実相寺さんが決めると。
「そう。それで3本の脚本を読んで、真ん中がちょっと毛色が違いすぎるなとか指摘するわけです」
—そうなんですよ。真ん中のパートが一番爆笑が起きていたんですが。
「真ん中、面白いでしょ。僕大好きなんです」
—真ん中こそが中野さんのテイストを全開にしたのかなとも思ったんですが。
「それはノーコメントで(笑)」
—ドイツ人が日本語をしゃべるところとかそうなのでは?
「ああ。あれは違います。現場のノリです」



■今回は『姑獲鳥の夏』よりもテイク数が多かった!
—この作品、音楽もまたいいですよね。
「あの曲、明るいでしょ。これはトリビア的なことなんですが、あの曲は実相寺さんのテレビデビュー作の音楽なんですよ。『でっかく生きよう』という作品の。最期の作品と処女作とをくっつけたという。無意識か意識的かは分からないですが。スタイリッシュですよね。こういう死に方はなかなか出来ないですよね。こういう生き方も出来ないですけど」
—カリガリ博士が登場する時に、テルミンで演奏される『ワルキューレの行進』もおかしかったですね。
「あれ、最高ですよね。どういう顔をして、あの飛行船を見ていいのやら。カリガリ博士の登場もおかしいんですよ。後ろにいて「皆さんごきげんよう」ってね。石橋さんに、『あれは面白かったですね』と言ったら、『ああ、70年代のね』というんです。『70年代って何のことですか?』と聞くと、『あのマイクの持ち方は全学連の持ち方なんだ。新宿でアジ演説をするときにはああやって持つんだ』と言われて(笑)。『ほら、やってみろ』という。どうも石橋さんの中で忘れがたい思い出らしいんですね。また、ああいう演説がうまい人がいるらしいんですよ。ちょっと泣かせる話を混ぜたりしてね。そして最終的にはみんなにこぶしを振り上げさせるらしいんですが。『あれはアパートか何かで練習したのかな』とか言ってましたけど」
—中野さんは、エキストラで出演されたとか。
「旅芸人が出てくるんですが、太鼓を叩くチンドン屋はみんな僕のお友だちで。是非是非この20年代のシルバー帝都に、友だちや僕とかが存在したかったんですよ。実相寺宇宙の登場人物になりたかったので、とりあえず手弁当で駆けつけました。そしたら、ものすごい厳しい演出で恐れおののきました。0.0何秒遅い!とか、17度こっちに向きなさい、とか。細かいところはすごく細かいんですね。
普通は、NGがあったら、『もう一回やってみようか』とか言うじゃないですか。そうじゃなくて、『今のは山田くんがオッケーだったら、オッケーのカットだったんだよね』とか言うわけです。ちゃんと責任の所在を明らかにして、何がいけなかったのか言うのは素晴らしいですね。私には出来ないですね(笑)。
しかも俺の連れてきた女の子たち、ギャルショッカーと呼んでいるんですが、彼女たちなんて、その辺を歩いている人ですから。遠足気分で来ていますから。それでもすごく怒られたりしてますから。『ヘタクソ!』って。本当に可哀想に(笑)。『今のは彼女が悪かったからダメです』と言われ。『すみませんね』と石橋さんに言ったりして。寺田農さんが2分くらい長台詞を言ったあとにNGを出したりすると、『申し訳ない! うちのギャルショッカーが』と謝ったり」
—実相寺監督は相変わらず早撮りでしたか?
「そうですね。でもこだわっているところはすごかったですね。加藤礼次朗さんが言うには、『姑獲鳥の夏』よりも全然テイク数が多かったらしいんですよ。だからすごく気合が入ってらしたんでしょうね。もちろん楽しげにリラックスしてましたけどね。
最後に飛行船が出てきて、戦後の焼跡みたいになるシーンがありますよね。あれ、再撮影ですもん。どうしても自腹を切ってでもあのシーンが撮りたかったんでしょうね。あそこは何か意味があるんでしょうね。元々あのシーンは台本になかったんだもん」
—なかったんですか。
「台本にはただナレーションがあるだけで、特に画は指定していなかったですから。そこに斎藤茂吉の詩を持ってきて、CGをいっぱい出して。わざわざチンドン屋さんを呼んで、レールを引いて、あれに何か秘密があるんでしょうね。で、カメラがバーッとひくと、そこは20年代なのにばっちりハイエースが写っていますからね。多分あれは舞台ばらしなんですよ。あれすらも、もう一つの入れ子で、現実の世界だということなんですよね。きっと」
—実相寺組ともいえるスタッフ、キャストについてはどう思いますか?
「実相寺さんの好きなカメラアングルとか、監督のいろいろな要求に応えられるようにチューンアップされたスタッフですよね。多分、こうすると実相寺さんは文句を言うであろうからこうしようといった具合に予想するらしいんですよ。でも実相寺さんは、さらにそれを上回る頭の切り替え方を持っていらっしゃる方で、いつもスタッフの予想を裏切るらしいんですよ。確かに今回は病で肉体は衰えていたかもしれないけど、むしろ精神は冴え渡っていたんじゃないですかね」
ちな坊のバッチというのがあるんですよ。あらいぐまのぬいぐるみのバッチなんですが。あれ、欲しかったな。でも、実相寺組という感じはあまりしなかったですね。それよりは実相寺部の人たちって感じですからね」
—科学者役のひし美ゆり子さんは久しぶりですよね。
「すっごい緊張してましたけど、始まれば、いつもの可愛らしい博士になっていましたね。ひし美さんは『プレイガール』のイベントの時に一緒になったんですが、男の人には頼らずに独立して、運命を切り開いて生きていく『プレイガール』のイメージがありまして。考えてみれば女の博士ってあんまりありませんでしたよね。素晴らしかったですね」
—最後に、これから映画を観る方にメッセージをお願いします。
「どうしても変身ものというと、男の子のものですか。最近は変身前の若い男の子を見る女性も多いようですが。でもこの作品は女性にも見てもらいたいですね。ゴスロリみたいなお姉ちゃんもこういう世界がもしかしたら好きかもしれないし。
これは大正ロマンで、ドイツ表現主義で、しかもカリガリ博士もロックンロールなので。きっとあなたの好きなものがひとつやふたつはあるはずだと思います」
執筆者
壬生智裕