TIFF アジアの風『時に喜び、時に悲しみ』プロデューサー、ヤシュ・ジョハール氏が語るマサラムービーの舞台裏
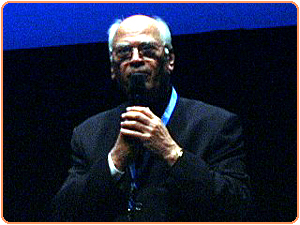
第15回東京国際映画祭「アジアの風」部門で上映されたインド映画は、エンターテイメントの王道をいくマサラムービー「時に喜び、時に悲しみ」だった。日本でもファンの多いシャー・ルク・カーンと東京ファンタで来日経験もあるカージョル、大物俳優のアミターブ・バッチャンとその夫人のジャヤー・バッチャン、そして若手人気スターのフリティク・ローシャンとカリーナ・カプールという、ヒンディ語映画圏の6大スターが競演し、2001年から2002年にかけて大ヒットを記録した。
映画自体は、ラブストーリーをふんだんに盛り込んだ家族愛もので、アミターブ・バッチャン演じる実業家の養子ラーフル(シャー・ルク・カーン)が、ふとしたことからアンジャリ(カージョル)と恋に落ち、駆落ちするまでのラブストーリーが前半。後半では、実業家の実子ローハン(フリティク・ローシャン)が、勘当された義兄ラーフルを探しにロンドンへ行き、カージョルの妹(カリーナ・カプール)と恋をしながら父と義兄の再会を画策する。華やかな演出のダンスシーンたっぷりの夢のように楽しい3時間30分の超長編で、今回の上映では、インド式に前半と後半の間に休憩時間が設けられた。
本作を監督したカラン・ジョハールは、98年にシャー・ルク・カーンとカージョル共演の初監督作品「Kuch Kuch Hota Hai」でいきなり大ヒットを飛ばし、ボリウッドでは注目の存在。残念ながら監督の来日はなかったが、プロデューサーとして長くインド映画界に関わってきた実父のヤシュ・ジョハール氏が出席しておこなわれた10月31日のティーチインは、マサラムービーの製作者のナマの声が聞ける貴重な場に。会場からの質問もマニアックなものが目立ち、そんなティーチインに感動したのか、ジョハール氏は途中から起立して答えていた。



観客A ●3つ伺いたいのですが、まず、私が初めて見たインド映画が4年前の「ムトゥ」なんですが、これはタミル語であって、今回のはヒンディ語ですよね。言葉の違いはもちろんですが、描き方とか作り方に何か違いはあるのでしょうか?
「インドには29の州があり、それぞれに言語を持っています。基本的には標準語といわれているのはヒンディ語という今回の作品で使っている言語です。もちろん感情の表し方は、州によって言語によって違っています。方言まで入れれば478という膨大な数がありますので、とてもカバーしきれません。が、ヒンディ語でだいたい皆さんわかっていただけるので、私どもはこういう形で作っています。ある意味ではオーバーな表現もありますが、映像を見るだけでフォローしていただけるということで対応しています。ひとつひとつ(の言語に合わせて)作っていたら本当にたいへんなことになってしまいますので」
観客A ●インドは世界一の映画制作国ですが、1990年の948本をピークに年々減少傾向にあります。これはどういうことでしょうか?
「残念ながら、これには経済的な理由があります。ひじょうに厳しい経済的な理由と、製作費がどんどんあがっていくということ。それから、公開期間が昔はそれなりに長く続けていたのが、最近は短くてぱっと公開して終わってしまいます。今年は、残念ながら興行的に大ヒットといえるものが1作しかなくて、そういう意味でインド映画界は苦労しているのが実情です」
観客A ●マサラ映画では踊りは俳優本人ですが、歌はほとんど吹替えですね。インドでは、歌える俳優はいないのしょうか? それとも、必要ないのしょうか?
「私は、音楽はとても大事だと思っています。ほとんどの場合、俳優が演技はできるのだけど歌えません。私としては、できるだけ声が似ている人、しゃべる声とか、もしも実際に歌ったらこんな声だろうという、できるだけ声が似ている人を探します。そして、できるだけうまく口パクを合わせるように。歌手を探し出すのも苦労していますし、俳優は口パクの練習でも苦労しています。この映画では、実際に歌っている俳優がひとりいます。この人は歌がすごくうまいということではないのですけれど、十分対応できるのでお願いしました」



観客B ●2つ質問したいのですけど、まず配役。アミターブ・バッチャンさんとシャー・ルク・カーンさんとフリティク・ローシャンさんを選ばれてますね。アミターブ・バッチャンさんは80年代の代表的なスターですし、シャー・ルク・カーンさんは90年代の、フリティク・ローシャンさんは2000年代の代表する俳優さんだと思います。このような方を選ばれたのはとても面白いと思うのですが、どのように選ばれたのですか?
「(椅子から立つ)皆さんが、審査員と同じくらいに厳しいコメントをくださるので、私は立ちあがってお答えすることにします。
まず、私の息子(本作の監督)が『Kuch Kuch Hota Hai』を作ったときは、あれがデビュー作だったわけで若干25歳でした。当然、インド映画界としては“すごい新人が出てきた”という大きな期待をかけ、“まぐれだ”と言う人もいましたが、これからのことが大きな話題になりました。それで、責任を感じ、才能を証明しなければならないということになったわけです。
企画を考えるにあたって、何を観客の皆さんが必要としているかといえば、できるだけ皆が知っている豪華なスターが一緒に出ること。先ほど挙げられたスターは、それぞれで1本の映画に主演できるような人たちなので本来競演は難しい。それに、自分のキャリアがダメになるような作品には絶対に出ない。唯一の私の利点は——いちばん始めにアミターブ・バッチャンをキャスティングできたのですが、何故それができたかというと、昔、私は彼と2本仕事をしたことがあったので、それでOKがもらえたのです。シャー・ルクもカジョールも知っていました。フリティクは、最初に会った時はまだ学生でした。彼はこの映画に出たころには大スターになっていましたが。これは、本来ならば、とても集められないような豪華なキャストです。母親役のジャヤー・バッチャンさんもベテラン女優なんですが、役をとても気に入ってくれました。そのほかも、友達だったということ、そして、それぞれが自分の役をとても気に入ってくれて、何人もの俳優の出演が可能になりました。正直言って、ほとんど普通でしたら不可能なキャストだと思います」
観客B●イギリスよりもインドが素晴らしいということを訴えられていると感じたのですが、未だにインドの方はイギリスに対してある種の敵対的な、あるいは脱却したいというものがあるのですか? そういう要素を映画に入れると観客にウケるのでしょうか?(クリケットのエピソードなど)
「若い人たちがどんどんロンドンに留学しているのは事実です。それから、200年にわたってイギリスがインドを植民地支配していたのも事実ですが、独立から50年が経ちました。ほとんどの人がイギリスを許す状況にあり——もちろん何かそういうことが持ち込まれると未だにギクシャクすることがないとは言いませんけれど——そのことは今回ここで話すことではないと思います。そのようなことが入っているように思われたのかもしれませんが、必ずしもそうではありません。今、関係としては良好で、将来を見通していこうということで脚本を書いています。
分かっていただきたいのは、少年がお母さんに捧げて国歌を歌うシーン。その後ろのほうで(イギリスの人たちが)唱和してくれたわけですけど、あれもこれからもこういう関係でいたいという我々の気持ちをわかるようにということでああいう場面が入りました。
クリケットなんですけど、実はひじょうに意味のあるスポーツです。サッカーでは誰が得点を入れても構いませんが、クリケットは特定のポジションの人がある意味ですべての勝利を決めてしまいます。その人が頑張らないと、他の人がどんなに頑張ってもダメなわけです。そこで、何度も繰り返す言葉がありましたよね、“目を閉じて、心を開いて”という。あの言葉が、ある意味ではとても大事なものだと、私は伝えたかったのです」
観客C ●今まで作ってこられた映画の中の音楽やシーンを連想させるようなところがありました。これは、今までのものを使うことで伝統を表したかったのか、それとも、いろいろなスターを集めたということを曲を聴いただけでわからせる意味合いがあったのでしょうか?
「すべての質問が的を得ている質問で、たいへん嬉しく思います。
あらゆることをたいへん細かく計算しながらやっています。音楽もそうです。そういう意味では、必ずしも同じサウンドワークは使うまいと考えているのですが、それと同時に、前作の主人公がどうなったか、たとえばあの女性になったということは音楽を使って同じように踊れば伝わるじゃないですか。いつもくださっている観客の皆さんは、音楽についてもイメージを持っているので、そのイメージをひっぱり込んでくだされば——特にロマンスの関係は正直言って映画ではどんどん長くなってしまうので、そのへんのところはすぐにわかってくださる。前作の音楽をすごく気に入ってどうしても使いたかったこともあります。本作と前作は違っていて、決して繰り返しをするつもりはないのですけれど、そういう意図があります」
司会●最後にメッセージはありますか?
「誠にありがとうございます。3時間以上の長い上映、そして30分にわたるこのようななかでの皆さんの忍耐に感謝します。次の映画も頑張って作りたいと思います。日本もすばらしい技術を誇る国だと思います。インドにもたいへん素晴らしい文化があります。これから、日本とインドの映画も含めた結びつきをより深めていきたいと思います」
執筆者
みくに杏子